化学実験、バイオ実験のノウハウなど、毎日の実験・分析に役立つ情報をお届け。
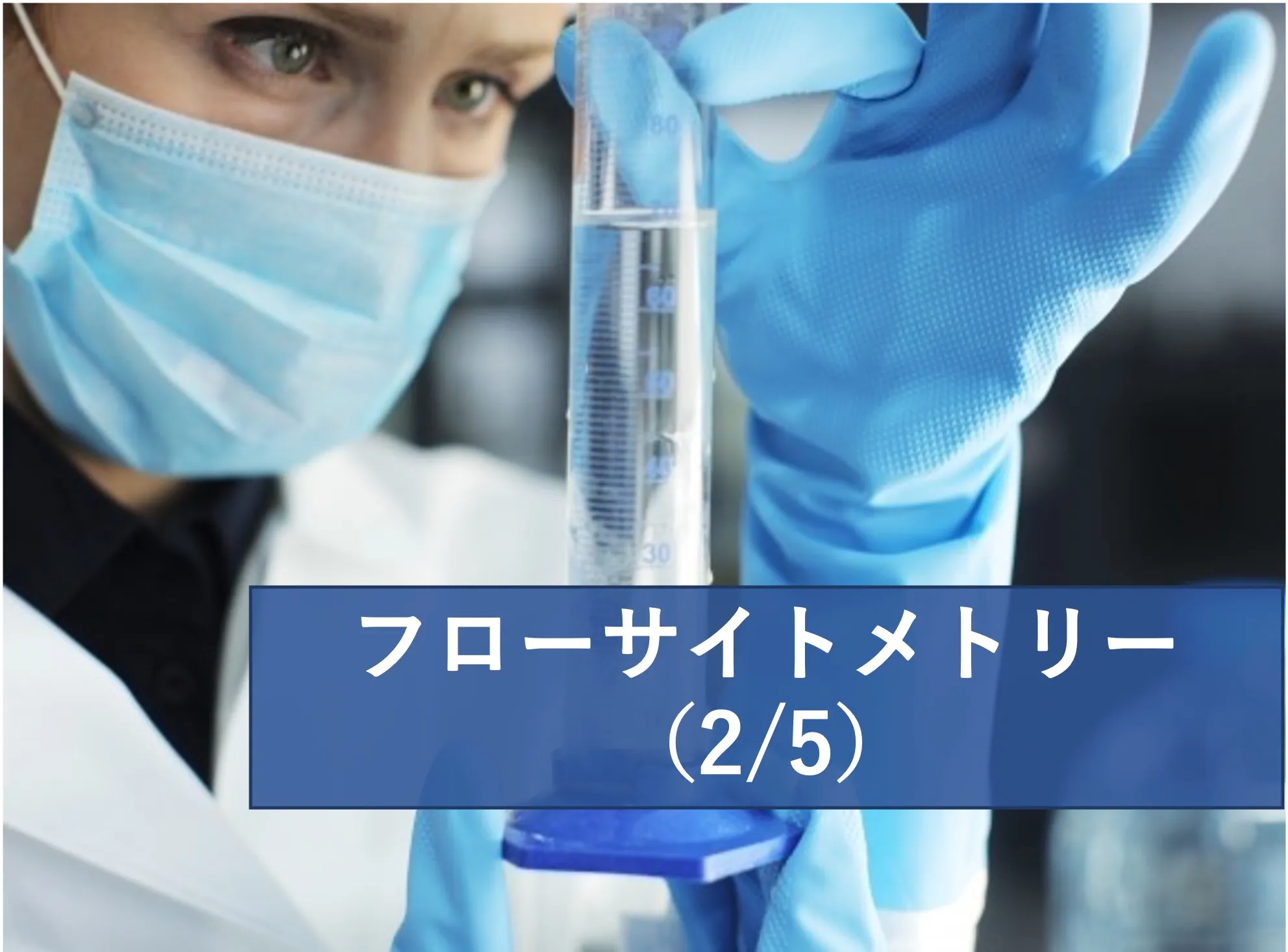
プロトコル −細胞表面抗原や細胞内抗原の蛍光免疫染色による細胞解析−
前項で概要を説明したように、フローサイトメトリーを用いると、細胞表面や細胞の内部に存在する目的タンパク質の発現量を定量的に解析することができます。一方で、これを実現するためには、目的タンパク質を抗原とした蛍光免疫染色をあらかじめ行うことも欠かせません。ここでは、蛍光免疫染色を用いて細胞をフローサイトメトリー解析するプロトコルの例をご紹介します。(細胞表面の抗原を染色する場合と細胞内部の抗原を染色する場合では、それぞれ前処理の方法が異なる点に注意する)
1. 試料の準備
- 細胞の収集:血液、培養細胞、組織などから目的の細胞を分離してチューブなどに回収します。
- 試料中の細胞数は、通常1 x 106細胞を目安に準備します。
- PBS(リン酸緩衝生理食塩水)などの適切なバッファー中に細胞を懸濁した試料を調製します。
2. 細胞の固定
- 試料を4%パラホルムアルデヒド(PFA)などで10~20分間、室温でインキュベートすることで、細胞を固定します。
- 洗浄:PBSなどで細胞を懸濁して、遠心後に上清を捨てます(細胞の洗浄)。これを1~2回繰り返します。
3. 細胞膜透過処理(細胞内部の抗原や標的を染色する場合に実施)
- 透過処理:固定した細胞をTriton X-100(0.1%~0.5%)やサポニンなどの界面活性剤を含むバッファーで、10分~20分間インキュベートします。この処理により、細胞膜に部分的に穴が開き、抗体が細胞内部に浸透できるようになります(透過処理)。細胞内部の抗原に対する免疫染色や核染色を行う際には、これらの染色剤が細胞膜透過処理は不可欠です。
- 洗浄:PBSなどで細胞の洗浄を2~3回行います。
4. ブロッキング処理
- 抗体がFc受容体などを介して細胞に非特異的に結合することを防ぐために行います。10分~30分間、室温または4度で、ブロッキング剤(Fcブロッカーや正常血清など)中で細胞をインキュベートします。
- 洗浄:PBSなどで細胞の洗浄を1~2回行います。
5. 抗体反応
- 蛍光標識された1次抗体(例:FITC、PE、APCなど)を適切な濃度で試料に添加し、通常30分~1時間、4度または室温で、暗所でインキュベートします。標的抗原に特異的に結合することが事前に確認された抗体を使用します。抗体に標識された蛍光色素間で蛍光スペクトルが重ならない条件で、多重免疫蛍光染色を行うこともできます。
- 洗浄: PBSなどで細胞の洗浄を2~3回行います。非特異的に細胞に結合した抗体を除去することで、シグナルとノイズの比を良化することができます。
- *死細胞除去(オプション):プロピジウムヨウ素(PI: Propidium iodide)や7-AADなどを用いて死細胞を染色する。固定処理を行っていない細胞試料に対して実施することで、後の解析の過程で死細胞を識別することができます。これらの染色剤は生細胞の細胞膜を透過しないため、生細胞は染色されません。
6. 再懸濁
- 細胞をフローサイトメトリーで測定するために、PBSまたはFACSバッファー(PBS + 1% 牛血清アルブミン+ 0.1% NaN3)に細胞を再懸濁します。
7. フローサイトメトリー
- 蛍光の測定:フローサイトメーターに調製した細胞液をセットします。適切な励起波長のレーザーと適切な検出フィルターを使用して、各抗原から得られる蛍光を特異的に検出する条件で蛍光強度を測定します。特に多重免疫蛍光染色の場合には、蛍光色素間の漏れ込みが生じない条件で蛍光取得を行います。
- 散乱光の測定:FSC(前方散乱光)の強度の時間変化をもとに細胞の大きさを測定します。SSC(側方散乱光)の強度の時間変化をもとに細胞の内部の複雑さを測定します。
8. データ解析
- ゲーティング:全細胞を対象に、散乱光や蛍光強度のヒストグラムやドットプロットを作成します。全細胞の中から解析対象とする目的の細胞集団を選定します(ゲーティング)。
- 死細胞除去:必要に応じて、全細胞中に存在する死細胞を解析対象細胞のゲートから除外します。
- 蛍光強度:ゲート内の細胞集団に着目して、各抗原タンパク質に由来する蛍光強度の値を発現強度として評価します。当該タンパク質の発現が既知である陽性対照細胞、および発現していないことが既知である陰性対照細胞を同様の方法であらかじめ解析し、参照試料とすることで、目的の試料の解析対象細胞における当該タンパク質の発現レベルを評価します。
細胞表面抗原や内部抗原の発現をフローサイトメトリーで解析することで、複数種類の細胞集団が混在した試料の中から、特定の細胞集団に着目し、その細胞集団の細胞構成や刺激に対する変化を定量的に明らかにすることができます。
抗原の種類や使用する蛍光色素の組み合わせによって、多様な細胞集団解析がデザインでき、フローサイトメトリーはこれからも細胞集団によって形作られる生命の理解に欠かせない技術です。
*監修
パーソルテンプスタッフ株式会社
研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)
研修講師(理学博士)
この記事は、理系研究職の方のキャリア支援を行うパーソルテンプスタッフ研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)がお届けする、実験ノウハウシリーズです。
過去の記事一覧:実験レシピシリーズ
関連記事Recommend
-
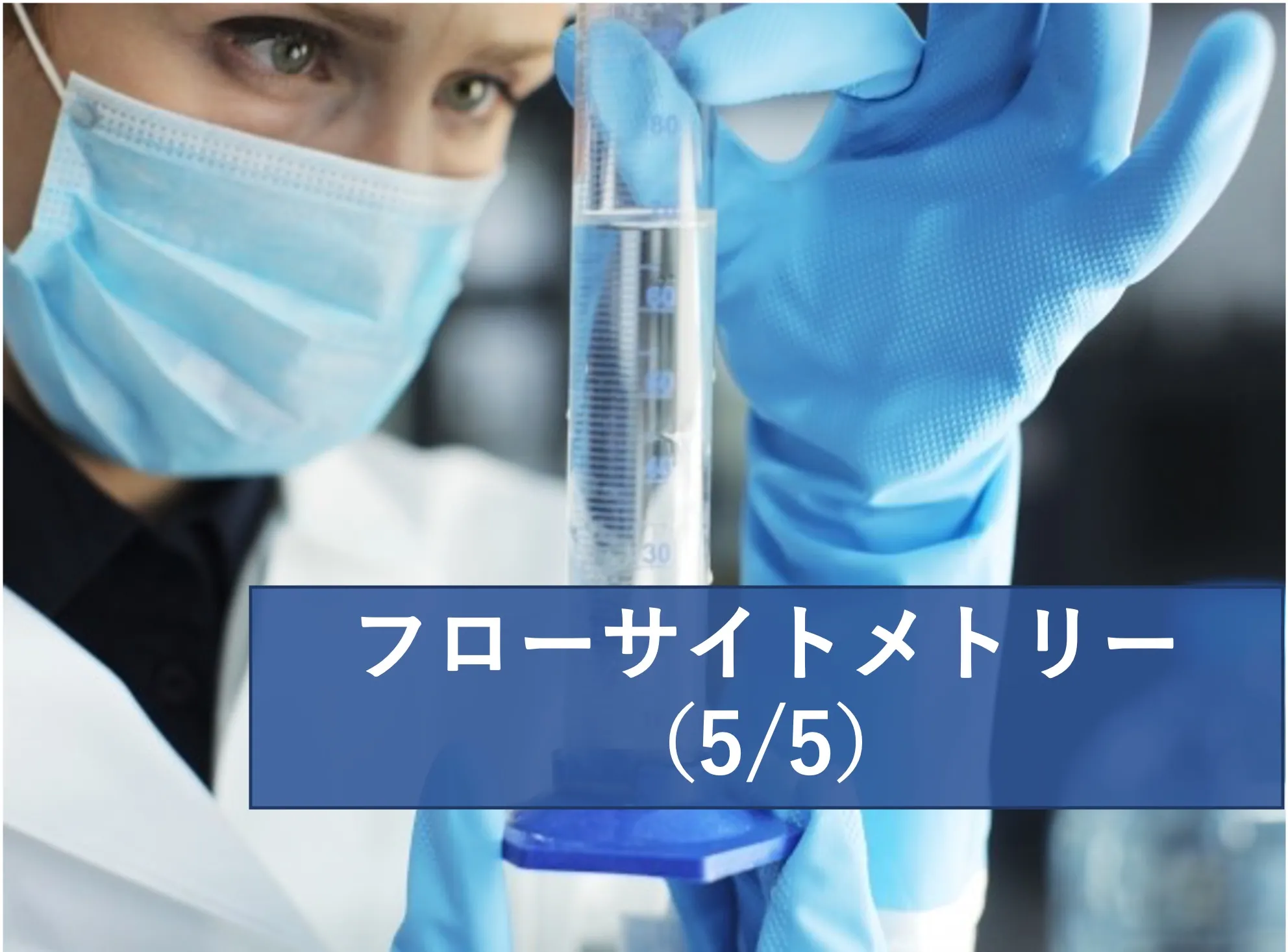
フローサイトメトリー(5/5) フローサイトメトリーを用いたセルソーティング
リケラボ実験レシピシリーズ
-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?
-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?
-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)
-
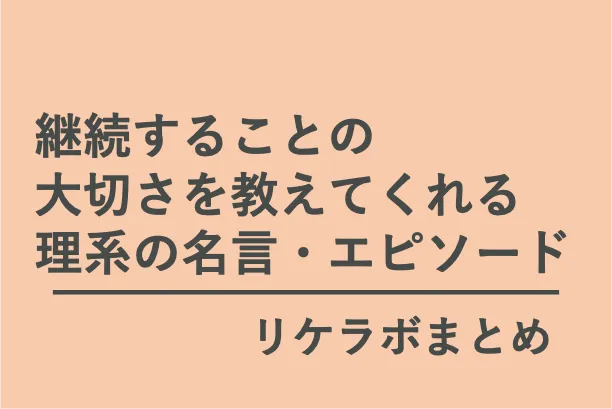
「継続することの大切さを教えてくれる理系の名言・エピソード」(リケラボまとめ)
-
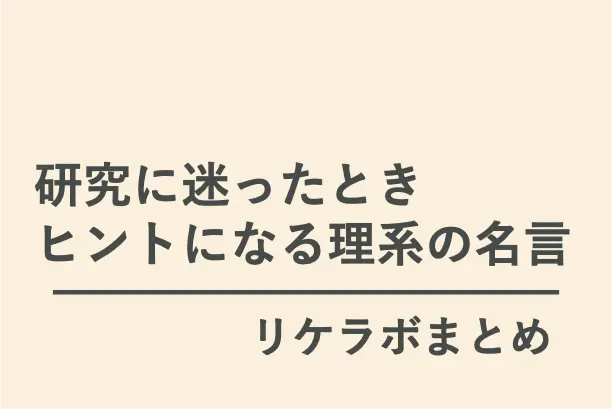
「研究に迷ったときヒントになる理系の名言」(リケラボまとめ)
-
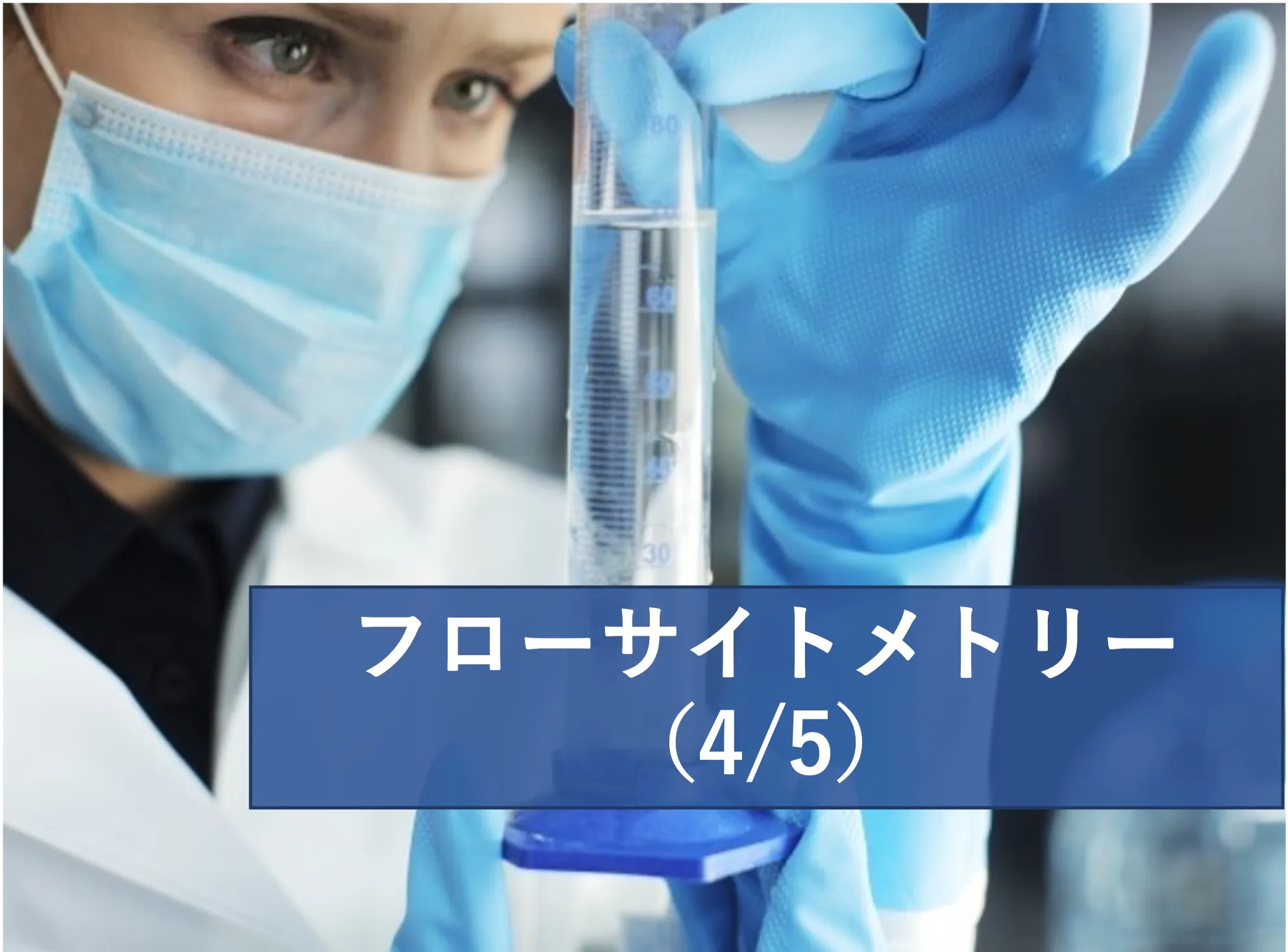
フローサイトメトリー(4/5) フローサイトメトリーを用いた細胞周期の解析
リケラボ実験レシピシリーズ
-
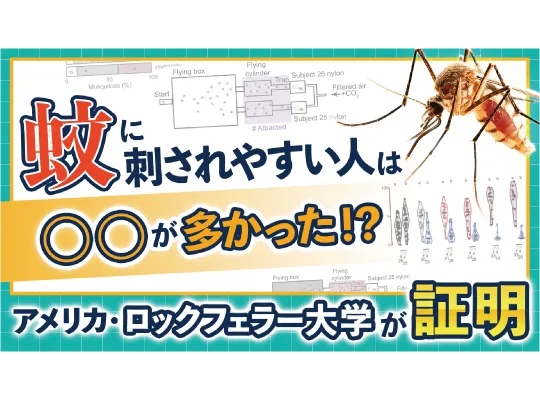
【動画解説】夏の強敵 “蚊に刺されやすい人”にはある共通点があった・・・!
-
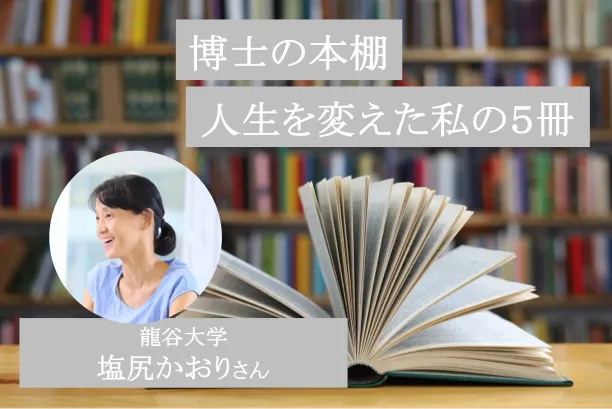
植物と虫の“匂い”を通じた会話を探究する生態学者、塩尻教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第12回)│龍谷大学 塩尻かおりさん
-
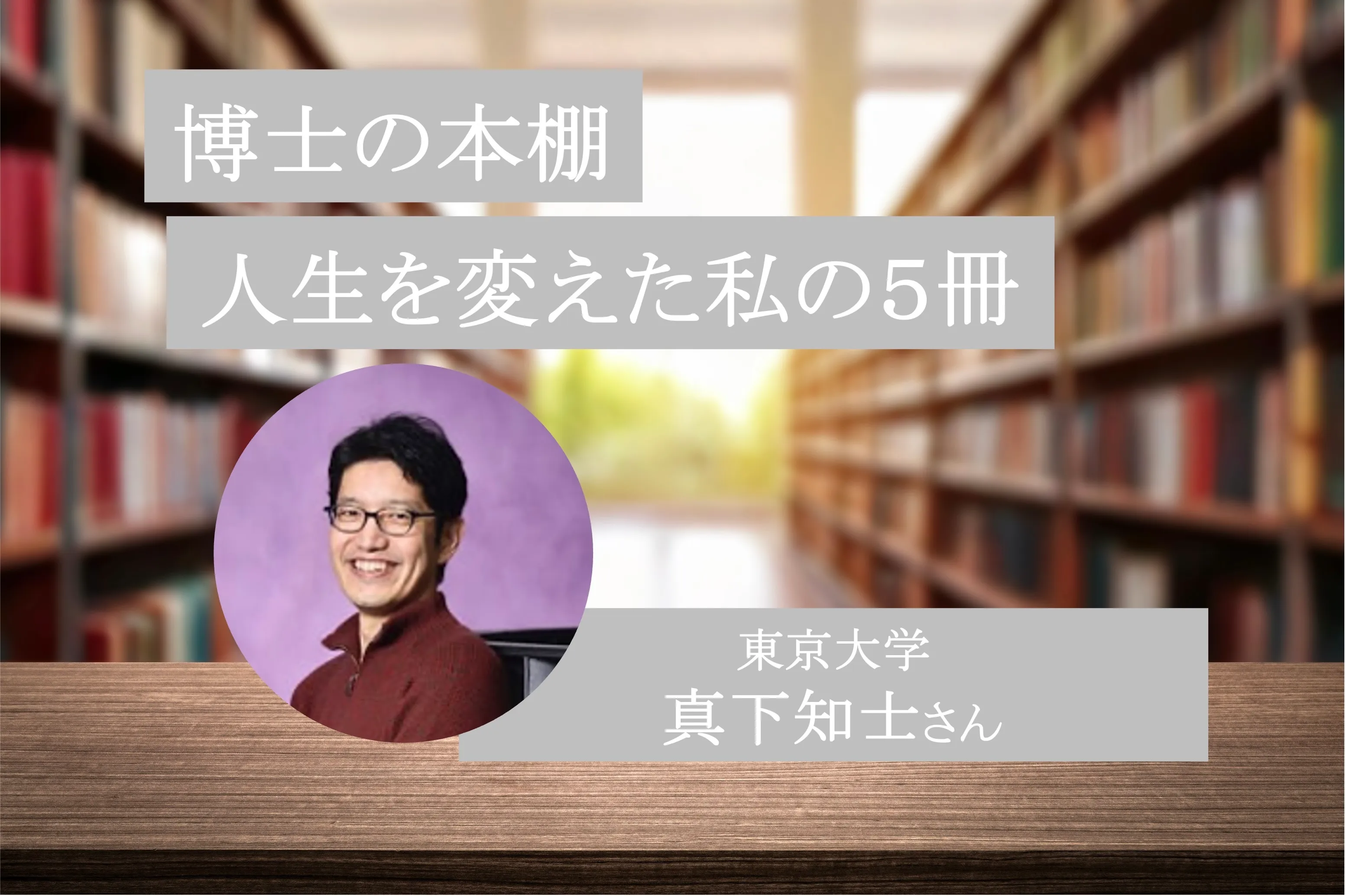
進化する生命科学の探究者、真下教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第11回)│東京大学 真下知士さん



