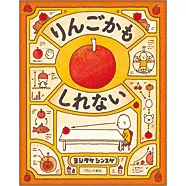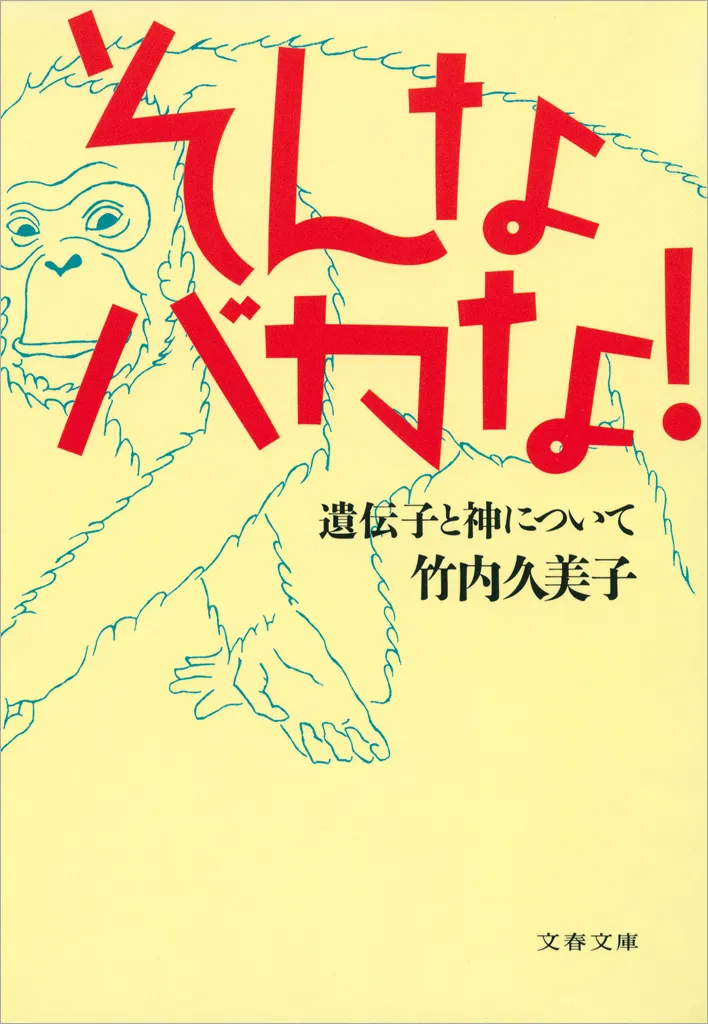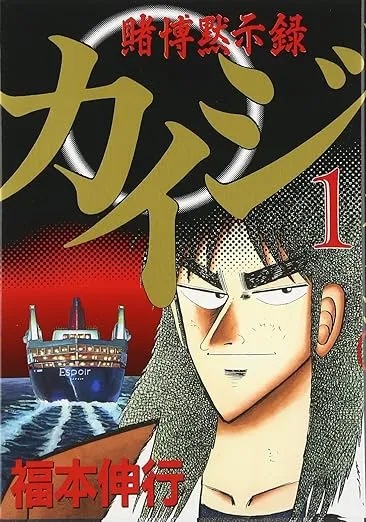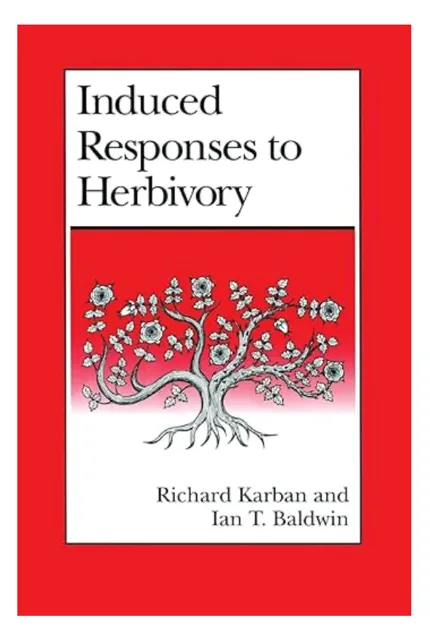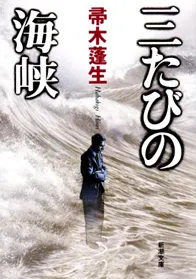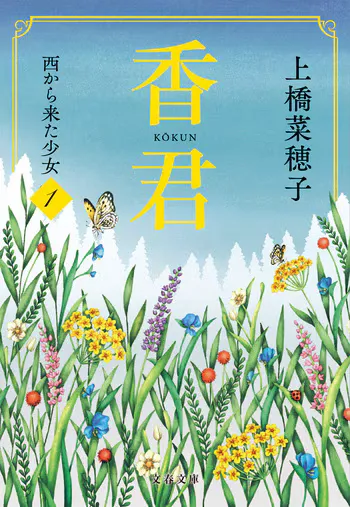頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!
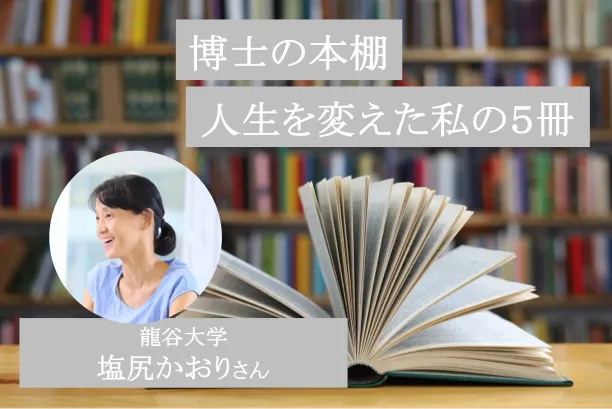
第一線で活躍する理系博士たちは、いったいどのような本を読み、そこからどんな影響を受けてきたのでしょうか。ご自身の人生を語る上で外せない書籍・文献との出会いを「人生を変えた私の5冊」と題し紹介いただく本企画。
第12回にご登場いただくのは、植物が発する“匂い”を手がかりに、生きもの同士の情報伝達や相互作用を読み解く研究を続ける、龍谷大学農学部の塩尻かおりさん。植物の“声なき声”をとらえようとする塩尻先生が、これまでの人生と研究をかたちづくってきた本の数々を語ってくださいました。
塩尻 かおり(しおじり かおり)
京都府生まれ。北海道大学で生態学を学び、京都大学農学研究科へ。昆虫と植物の相互作用の研究で修士課程および博士課程(農学)を修了、博士(農学)。カリフォルニア州立大学デービス校にて海外特別研究員(日本学術振興会)、京都大学生態学研究センターにて特別研究員(日本学術振興会)、京都大学白眉センター助教を経て、2015年4月より龍谷大学農学部植物生命科学科講師、2019年3月より同准教授、2021年4月より現職。(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)
『りんごかもしれない』
テーブルの上の“りんご”をめぐって、「でももしかするとこれはりんごじゃないかもしれない……」という想像が次々に展開していく、ヨシタケシンスケさんの代表作のひとつと言える絵本です。
子ども向けと侮るなかれ、大人が読んでもハッとさせられる一冊です。この本と出会ったのは、一番上の子どもが5歳くらいの頃だったと思います。ぷぷぷと笑えるのに、「たしかに、あるかも!」と考えさせられてしまう。その発想の豊かさと自由さに、子どもと一緒になって夢中になりました。
“これが正解”と決めつけず、“こんな見方もある”と受け入れる。その柔らかい視点は、まさに研究に求められるものと同じだと感じます。研究でも、一つの現象をどのように切り取るかで、見えるものはまったく変わります。多様な可能性を想像すること、固定観念にとらわれないことの大切さを、この絵本は読み返すたびにあらためて教えてくれます。
『りんごかもしれない』
著者:ヨシタケシンスケ
出版・書影引用元:ブロンズ新社
『遺伝子と神について そんなバカな!』
動物の不思議な行動を、科学的な視点でユーモラスに解き明かす一冊です。私にとっては、生態学に興味を持つようになった原点ともいえる本です。浪人時代、生物の授業で動物行動学に触れたときにこの本を知り、読んでみたら、遺伝子が生物の行動を操っている!?と、その衝撃に一気に引きこまれました。
この本との出会いを通じて、進化や生態の複雑な仕組みを“遺伝子の視点”から読み解くという考え方に初めて触れ、単純に「めちゃくちゃ面白い」と思いましたし、その考え方が少しずつ自分の中に根づいていく感覚もありました。特に、生物の行動原理が「種の保存」ではなく「(自分の)遺伝子の保存」であるという見方を知ったとき、自分の価値観がガラリと変わったのを覚えています。それまで不可解に思えていたアリやハチなどの社会性昆虫のふるまいが、すべて遺伝子の原理で説明できる。この“見え方が変わる”感覚が、ものすごく新鮮であると同時に、深く腑に落ちたんです。
この本を入り口に、進化生物学の古典的名著であるリチャード・ドーキンスさんの『利己的な遺伝子』にも手を伸ばすことになりました。そちらの本からももちろん大きな影響を受けましたが、研究者としての進路を切り開く最初のきっかけを与えてくれた一冊という意味で、今回はこの『そんなバカな! 遺伝子と神について』をチョイスしました。
『遺伝子と神について そんなバカな!』
著者:竹内 久美子
出版・書影引用元:文芸春秋
『賭博黙示録カイジ』
極限の心理戦を描くギャンブル漫画『賭博黙示録カイジ』。初めて読んだのはたしか大学生の頃で、誰かが研究室に持ち込んだ単行本を何気なく手に取ったのがきっかけだったと思います。
特に印象に残っているのが、最序盤に登場する「限定ジャンケン」です。プレイヤーには星3つと、グー・チョキ・パーのカード各4枚ずつが配られます。配られたグー・チョキ・パーのカードを使ってじゃんけんを行い、勝てば相手の“星”をひとつ奪え、制限時間内に全カードを使い切って星を3つ以上残していれば勝利──というのがこのゲームのルールです。一見シンプルなのですが、途中からプレイヤーが星やカードをお金で取引し始めたり、共謀や裏切りが発生したりと、状況が目まぐるしく変わっていく。その変化に伴って、戦略や勝率が大きく揺れ動きます。単純なはずのゲームが、状況の見極めとルールの解釈次第で一変する──その感覚が、進化や生態系の研究に通じるものがあると感じました。
実際の自分の研究のなかでも、たとえばキャベツをある虫Aが食べているとその虫の天敵を誘引する匂いがキャベツから放出されます。ところが、そこに虫Aとは別の虫Bも一緒に食べると、虫Aの天敵は誘引されなくなる――そんな例があります。また、これは私の研究とは別の話ですが、一般にアブラムシとアリは共生関係にあるとされていますが、アブラムシの数が多くなりすぎると、アリは一転してアブラムシを捕食し始めるのだそうです。こうしたように、少し状況が変わるだけで、それまで見えていた関係ががらりと変化することがある。この作品は、そんな研究に欠かせない視点を、いつも思い出させてくれます。
『賭博黙示録カイジ』
著者:福本 伸行
出版・書影引用元:講談社
『Induced Responses to Herbivory』
植物が虫に食べられたり病気にかかったりすると、虫や病気に対して抵抗性をもったり、より成長したりするという誘導反応が起こる。その誘導反応の一つに今までとはちがった “匂い”を放出する。その匂いが、植物を食べている虫を食べる虫を呼び寄せたり、他の植物に防御の準備をさせたりする。一見、静的にみえる植物の動的な現象に関する専門書です。大学院のときに読んだ本で、私にとって初めて最後まで読み通した英語の本でもあります。
それまで私にとって英文の文献といえば「必要だから読むもの」「我慢して読むもの」だと思っていたのですが、これは違いました。専門的な内容なのに、文章が驚くほどわかりやすくて、とにかく読み心地がいい。英語の本でも読むこと自体が楽しいと思えた、初めての経験でした。
また、この本をきっかけに、著者のひとりであるリチャード・カルバン氏(現在は親しみを込めてRickと呼んでいます)の研究スタイルにも強く惹かれました。論文を読んでいくうちに「この人のような研究がしたい」と思うようになって、実際にRickの研究室に留学もしました。まさに私の人生を変えた欠かせない一冊ですね。
Rickの研究は、高価な機材を利用するのではなく、現場での観察やシンプルなアイディアに根ざした地に足のついたものが多くて、その柔軟で創造的な発想にはいつも驚かされます。たとえば一緒にフィールドワークをしていた際、ある植物が放つ匂いを他の植物に伝える実験を行うにあたって、その場ですぐに用意できたビニール袋と吸虫管を使って自分の呼気を使ってやってみると言い出し、初めはびっくりしましたが、これが案外、結果のアタリをつけるには充分なレベルでうまくいくんです。無駄をそぎ落とし、何より思い立ったらすぐに実行に移す姿勢に、強く影響を受けました。
現在もRick、そしてRickの奥さんであるミケーラとの交流は続いていて、ふたりが共著した『How to Do Ecology』の日本語訳にも関わっています(今度、第3版の日本語版が丸善出版から出る予定です)。
『Induced Responses to Herbivory』
著者:Richard Karban, Ian T. Baldwin
出版・書影引用元:University of Chicago Press
『三たびの海峡』
この本を読んだのは、海外留学中のことでした。まったく予備知識もなく手に取ったのですが、読み終えたあと、思わず「えええ……」と声が出てしまうくらい、衝撃を受けたのを覚えています。
戦後の混乱の中、朝鮮半島から日本、そして中国へと翻弄された日本人孤児の人生が描かれている作品です。そこには、日本という国がしてきたこと、そしてそれによって人生を狂わされた人たちがいるという現実が、まざまざと描かれていて、突きつけられるような感覚がありました。
当時、外国人の友人たちと日本の歴史や政治について話すことも多かったのですが、そのたびに「自分は日本のことを何も知らないな」と痛感していました。特に同じ東アジアの仲間である韓国や中国の人たちにとって日本がどう見えているのか、どういう記憶や感情を抱いているのか――そこに向き合う入り口を、この本が与えてくれたように思います。
最近、アメリカの情勢をニュースで見て、留学生のビザが突然停止されたり、大学への入国が一方的に拒否されたりするという話を知って、この本を読んだときの感情がよみがえってきました。ハーバード大学に通う学生たちですら、他の大学に移らざるを得なかったり、入国予定だった学生が入国できなくなったり、自分の意志ではどうしようもないことで、人生が大きく振り回されてしまうような状況が起きています。
一方で、私はこれまで、そうした外的な要因に進路を阻まれることもなく、自分がやりたいと思ったことを、そのままやれてきました。それは、誰かが築いてくれた平和で安定した時代の上に成り立っていたもので、決して当たり前ではなかったんだと思います。だからこそ、自分の意志で選べるこの環境に感謝しながら、悔いのないように、自分の意志で生きていかなきゃって、この本を読んだ時の感情とともにあらためて思い返しているところです。
そうした思いの原点として、私にとって忘れられない一冊が、この『三たびの海峡』です。
『三たびの海峡』
著者:帚木蓬生
出版:新潮社
番外『香君』
最後に番外として「あなたの人生を変えるかもしれない一冊」をぜひ紹介させてください。上橋菜穂子さんの『香君』(こうくん)です。
ファンタジー小説なのですが、私の研究テーマである「植物のかおり」が物語の中心を担っていて、読んでいて本当に驚きました。さらにこの小説の着想のもとになったのが、私の恩師である高林純示先生の著書だということも知って、親近感を覚えましたし、とても嬉しくなりました。そのご縁もあって、昨年、上橋菜穂子さんと高林先生の対談イベントを企画させていただいたのですが、それくらい私にとって思い入れもある作品です。
物語の中で植物のかおりは人の営みや政治、社会構造と密接に関わっているのですが、それらが科学的な整合性も保ちながら本当に自然なかたちで織り込まれているんです。たとえば、フェロモンや揮発性化合物が空気中をどう拡散するのか、気流や湿度によってどう影響を受けるか、といった自然現象の描写がとてもリアルで、専門家が読んでも「そうそう、そうなんです」と思えるくらい忠実です。科学的な知識をきちんと踏まえつつ、人類学や物語の力でここまで世界を立体的に描けることに、心を動かされました。
上橋さんの作品を読んで、「自分の知っていることや経験したことを、こんなふうに物語として昇華することができたら素敵だな」と思いました。研究の延長線上に表現があること、そしてそれを自分の言葉で編んでいくことの可能性を考えさせてくれた一冊です。
私にとっては、ただ扱っているテーマが近いというだけではなく、「研究者として、そして一人の人間として、自分の世界をどう表現していくか」という問いを与えてくれた、まさに“これから人生を変えるかもしれない”本でした。ぜひ皆さんも一度読んでみてほしいと思います。
『香君』
著者:上橋菜穂子
出版:文春文庫
▼塩尻かおりさんにご登場いただいた過去記事はこちら
この植物の匂いって一体なに? 素朴な疑問から始めて、真相に迫っていく塩尻教授の研究スタイル
関連記事Recommend
-
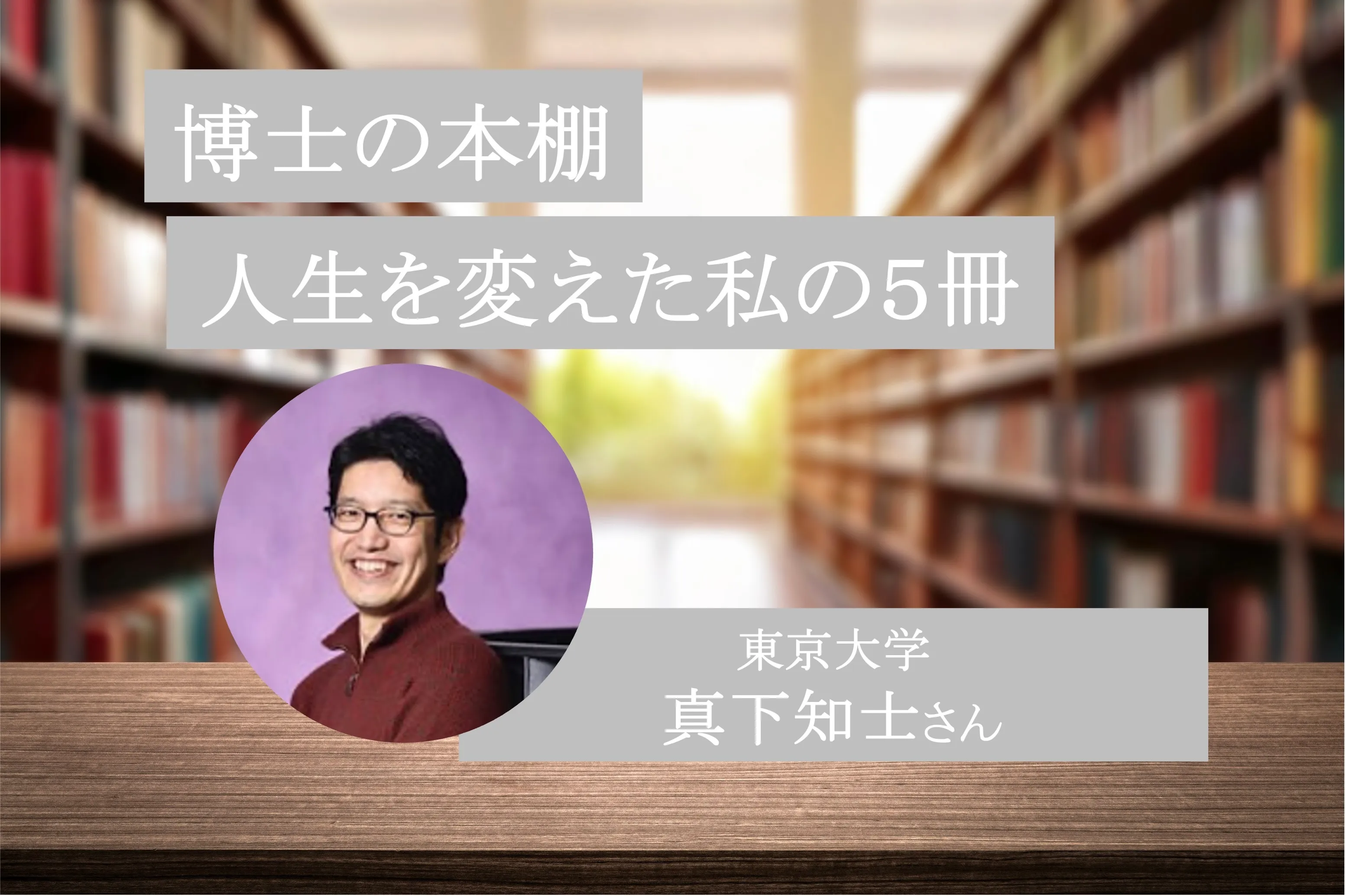
進化する生命科学の探究者、真下教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第11回)│東京大学 真下知士さん
-
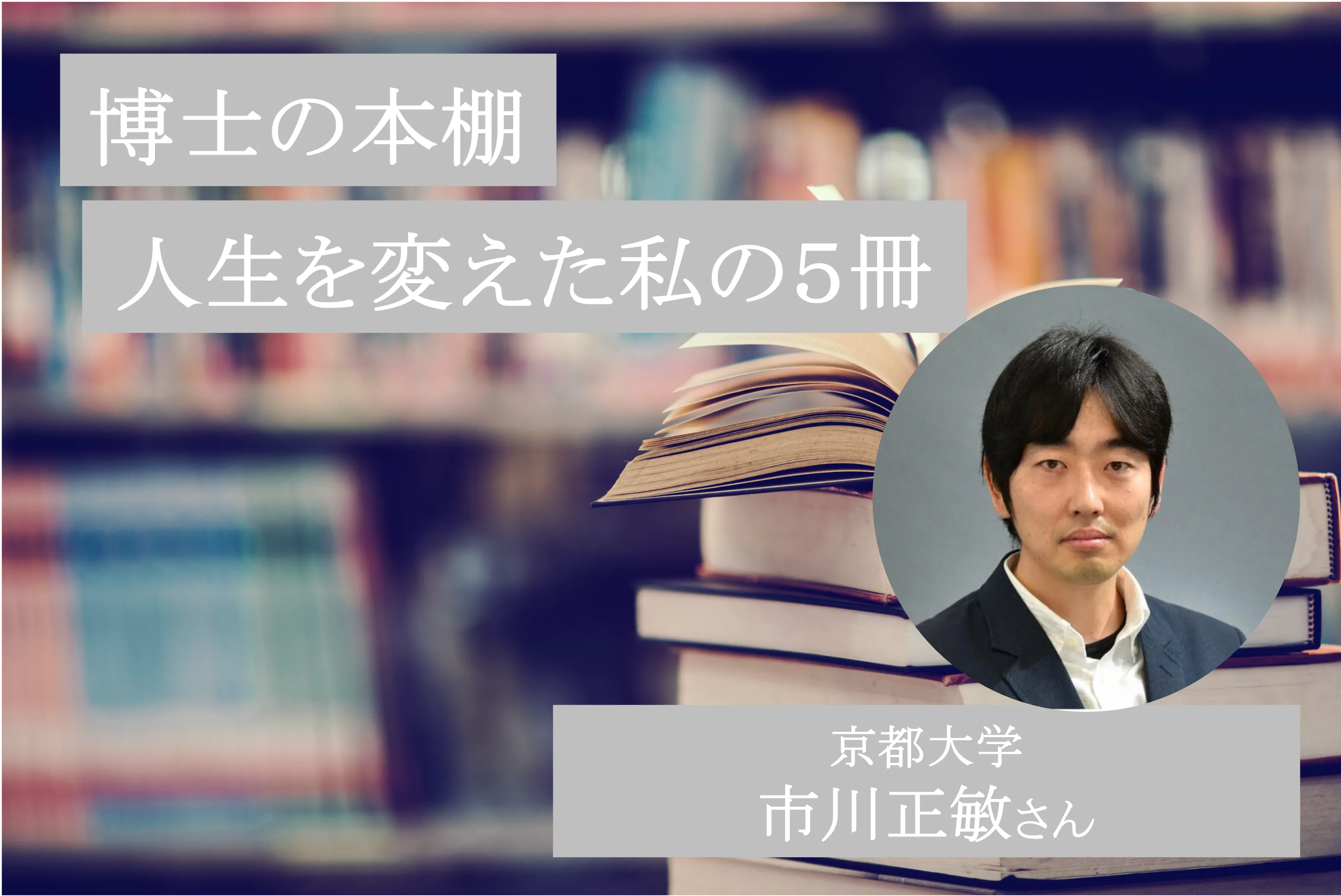
ソフトマター物理の観点から“生き物らしさ”を追求する市川正敏講師の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第10回)│京都大学 市川正敏さん
-
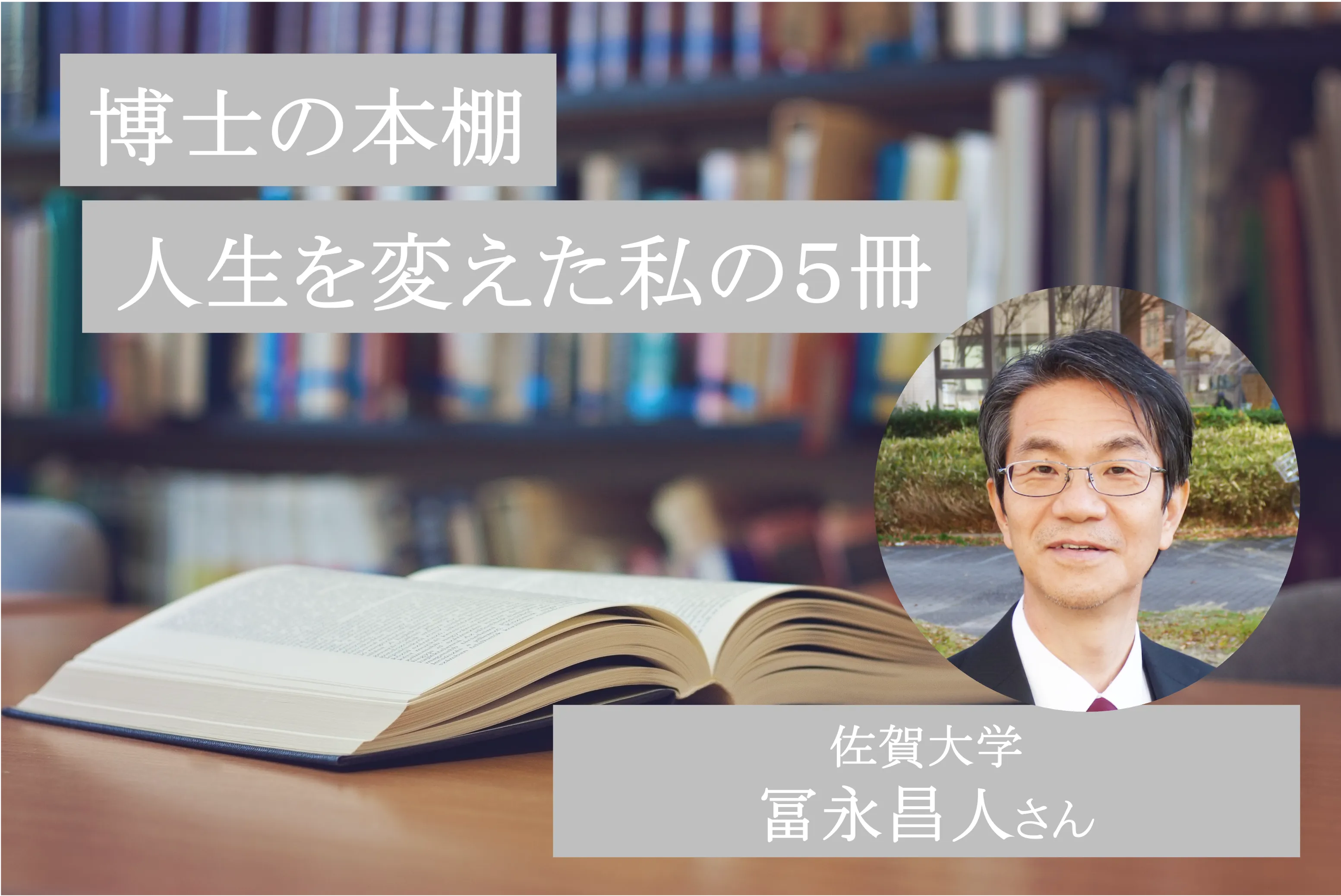
微生物が発電する「泥の電池」研究の第一人者、冨永教授に聞く「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第9回)│佐賀大学 冨永昌人さん
-
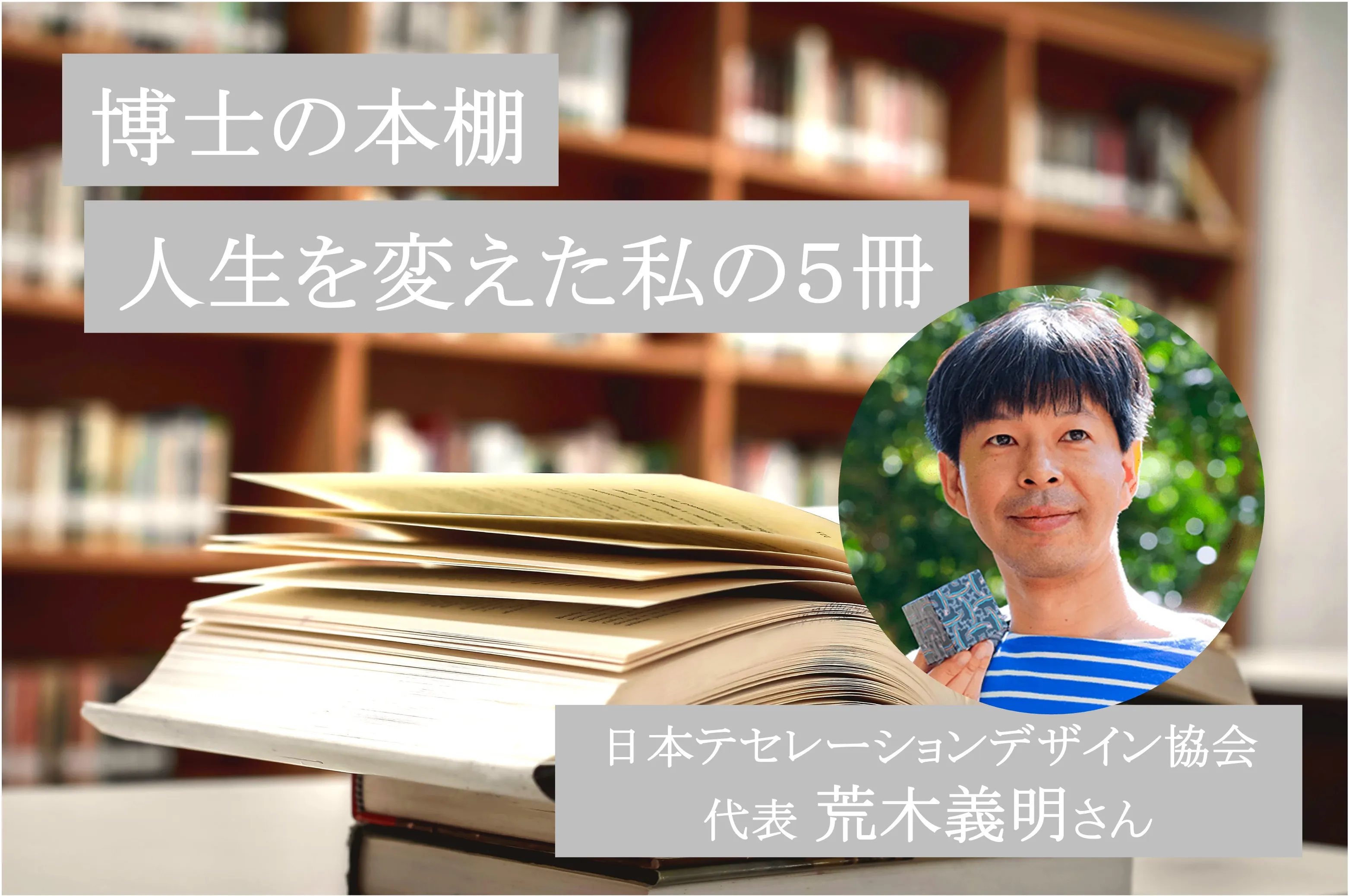
テセレーションデザインに見出す芸術性と法則。数学とアートを結びつける荒木義明先生の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第8回)│日本テセレーションデザイン協会代表 荒木義明
-
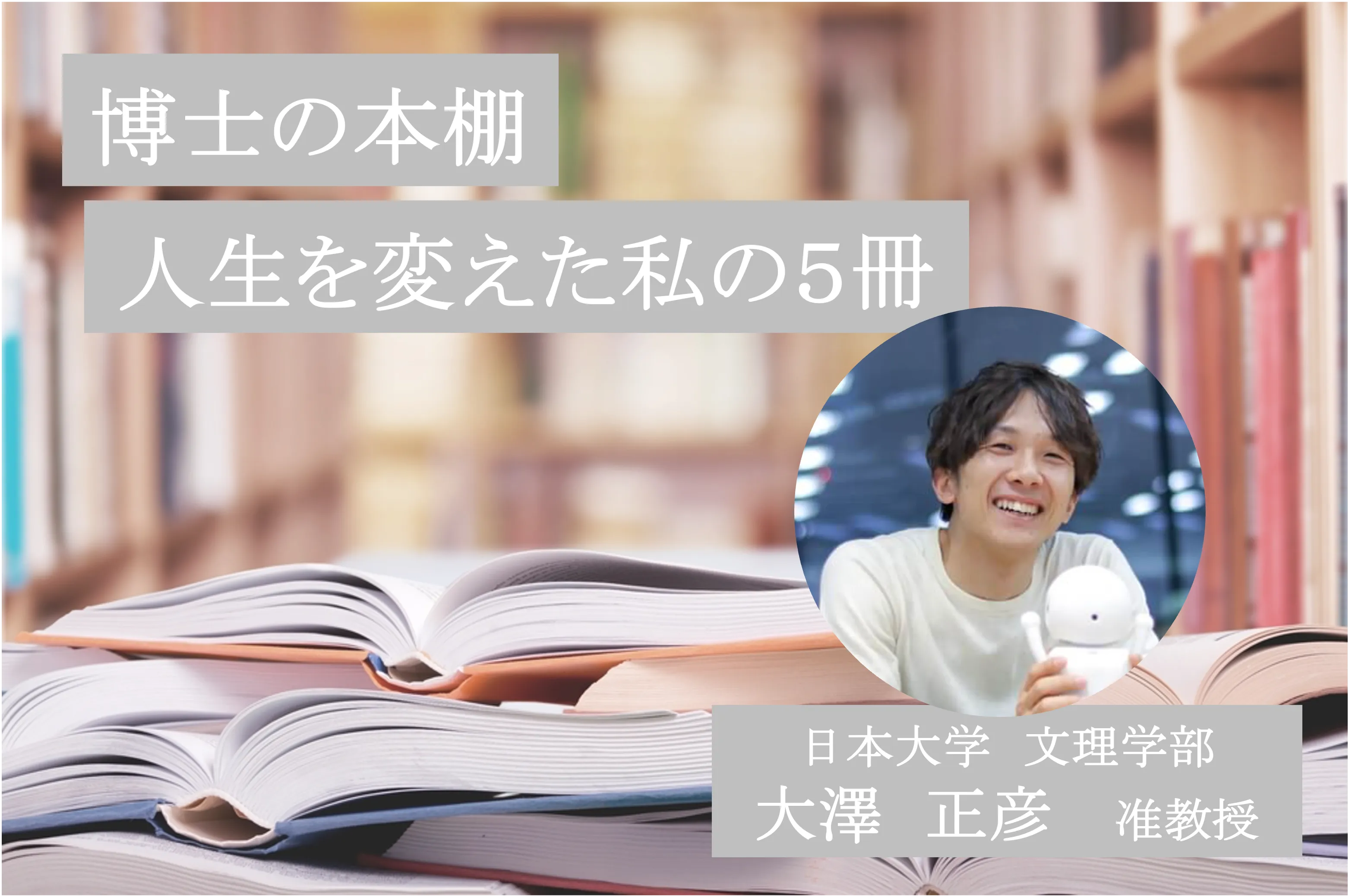
「ドラえもん®︎をつくりたい」人工知能開発の異端を育んだ個性のルーツとは?
博士の本棚(第7回)│日本大学 文理学部 大澤正彦准教授
-
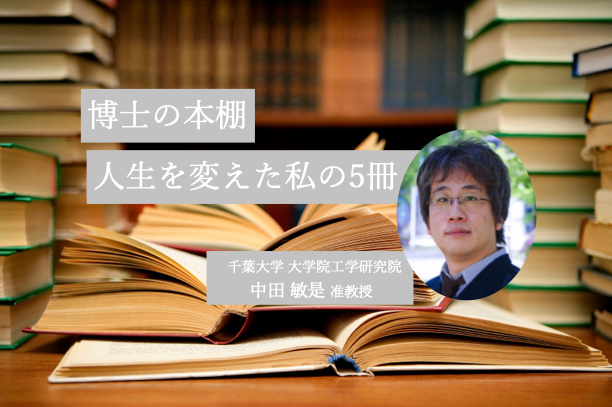
生物の飛行メカニズムを解明し、ドローンなどの機械工学へと応用する中田敏是准教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第6回)│千葉大学 大学院工学研究院 中田敏是さん
-
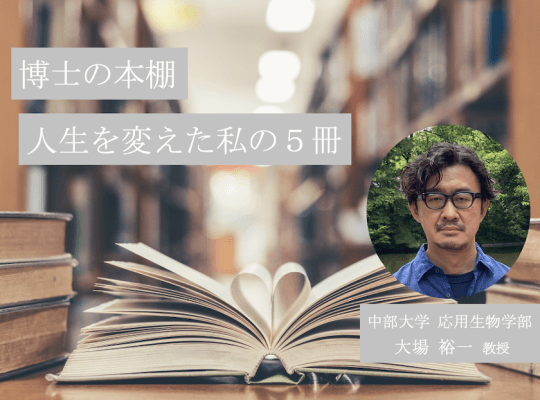
発光生物研究の第一人者、大場裕一教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第5回)│中部大学 応用生物学部 大場裕一さん
-
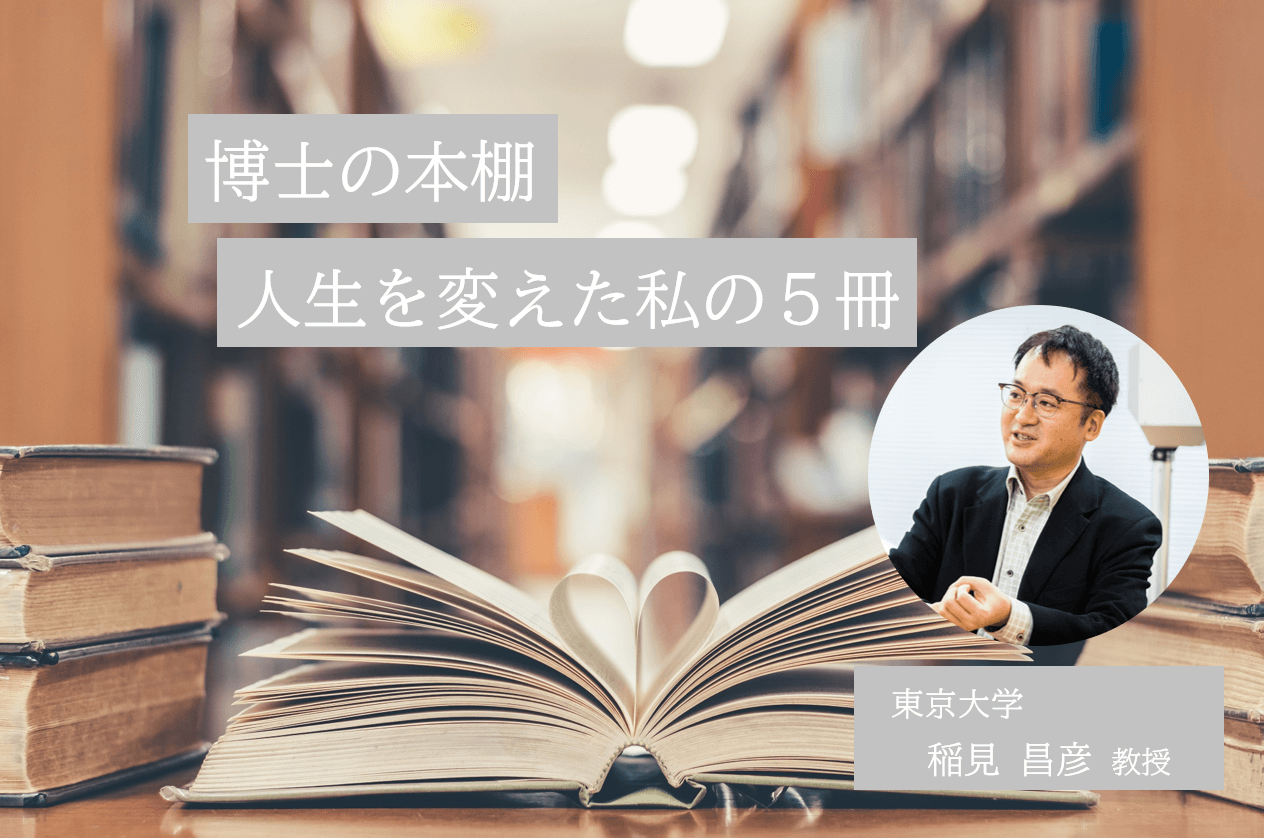
テクノロジーで人間の力を拡張する稲見先生の「私を形作った私の5冊」
博士の本棚(第4回)│東京大学 先端科学技術センター:稲見昌彦さん
-
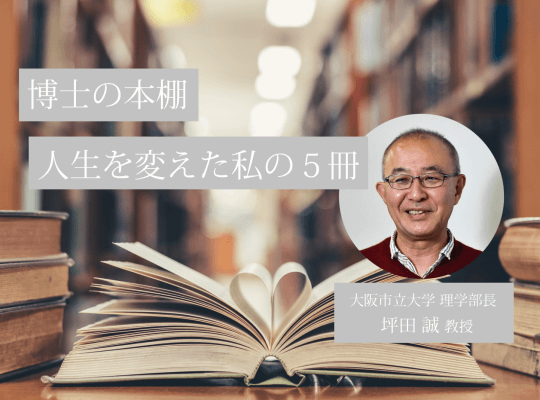
量子流体力学研究の第一人者、坪田誠教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第3回)│大阪市立大学 理学部長 坪田誠さん
-
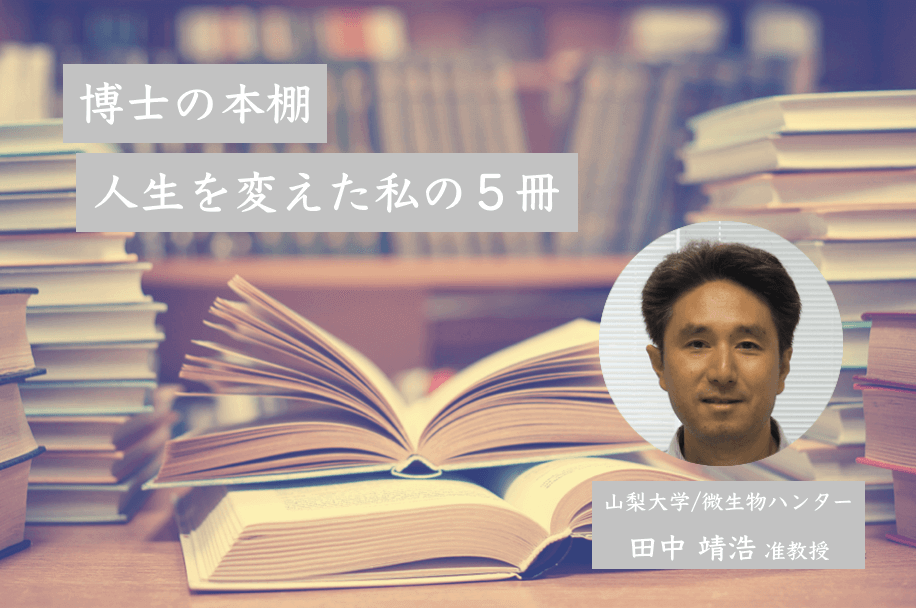
日本を代表する微生物ハンター・田中准教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第2回)│山梨大学生命環境学部 田中靖浩さん