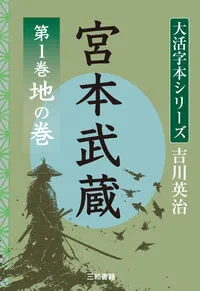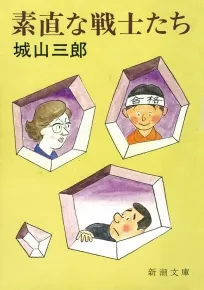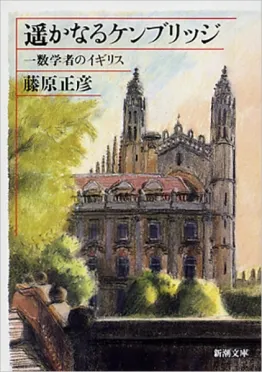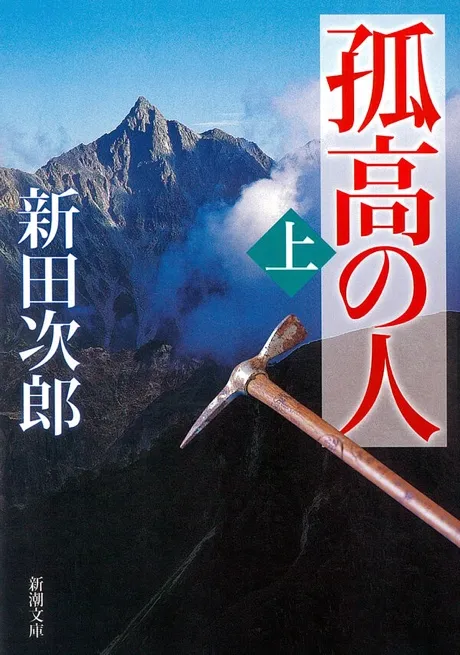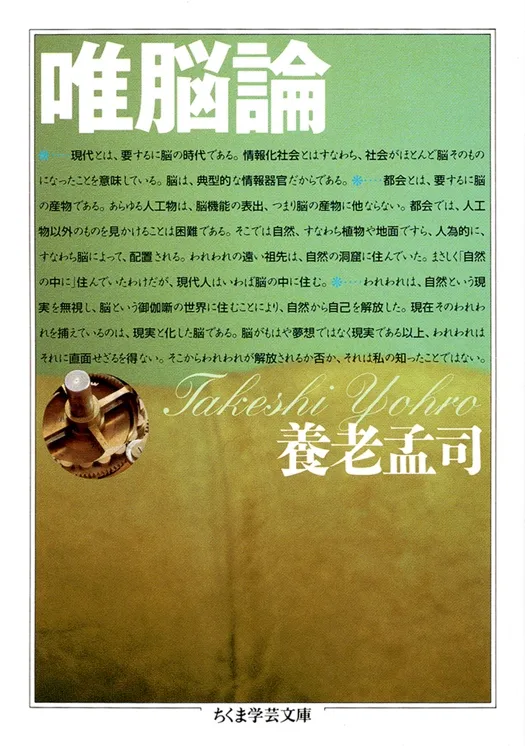頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!
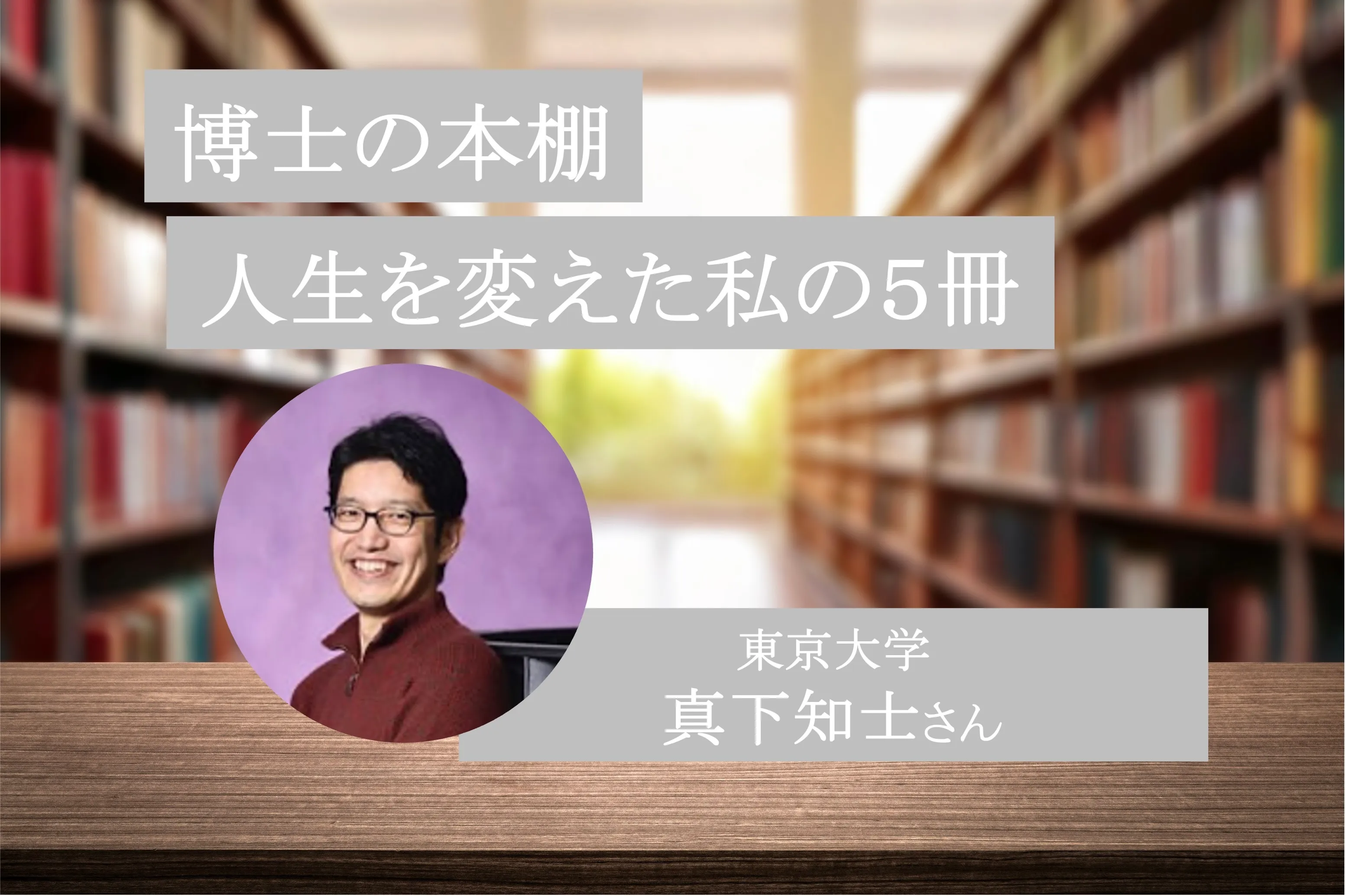
第一線で活躍する理系博士たちは、いったいどのような本を読み、そこからどんな影響を受けてきたのでしょうか。ご自身の人生を語る上で外せない書籍・文献との出会いを「人生を変えた私の5冊」と題し紹介いただく本企画。
第11回は、東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授の真下知士さん。以前にリケラボで、ゲノム編集技術とその応用について語ってくださった真下先生が、大きく影響を受けた本の扉を開いてみましょう。
真下 知士(ましも ともじ)
1994年、京都大学農学部卒業後、京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設研究生、97年、京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻修士課程修了、2000年、同博士課程修了、博士(人間・環境学/京都大学)。フランス・パスツール研究所免疫学講座ポスドク研究員を経て、2003年、京都大学大学院医学研究科附属研究施設産学連携研究員、同特定准教授を経て、2015年、大阪大学大学院医学系研究科附属動物実験施設准教授、2019年より東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)
ご挨拶 | 東京大学医科学研究所 実験動物研究施設 先進動物ゲノム研究分野
『宮本武蔵』
私が本を読むことの楽しさに目覚めたきっかけとなったのが、この『宮本武蔵』でした。小学生の頃、私は外で遊ぶのが大好きで、本を読むのはあまり得意ではありませんでした。しかし、ある日、家の本棚に並んでいた分厚い吉川英治の全集の中から『宮本武蔵』を手に取り、何気なく読み始めました。
最初はただの偉人の伝記として読み始めましたが、読み進めるうちにその奥深さに気づきました。武蔵の生き様、戦いの中での成長、そして彼の哲学——ただの剣豪物語ではなく、人としての在り方を問う作品だったのです。 私の父は本好きで、家にはさまざまな本が並んでいました。しかし、親から「本を読め」と言われると、逆に読みたくなくなってしまう性格でした。そんな中で自ら手に取り、読み進めるうちに「本を読むことは面白い」と実感しました。特に、小次郎との決闘の場面は強く印象に残っています。遅刻して小次郎を焦らせ、心理的に優位に立つ戦略に、当時の私は驚かされました。
この本を読んだことで「自分にもこんなにボリュームのある本が読めるのだ!」という自信も得た結果、本への抵抗感がなくなり、読書の世界に足を踏み入れることになりました。
『宮本武蔵』
著者:吉川英治
出版・書影引用元:三和書籍
※真下先生が実際に読んだのは、1936年~1939年に刊行された大日本雄辯會講談社版とのこと
『素直な戦士たち』
中高時代に影響を受けた本です。正直、手に取ったきっかけは覚えていませんが、これも家にたまたまあった本です。父は文学が好きで漢文をよく読み、母は推理小説が大好きでした。この本がどちらの趣味によるものかは分かりませんが、気がつけば手に取って読んでいました。
読んでみると衝撃的でした。受験戦争を描いた作品で、教育ママが子どもを東大に入れるために全力を尽くす。長男は期待に応えようと努力し続けるものの、うまくいかない。一方、ほったらかしに育った次男は意外とうまくやっていく。そんな対比が印象的でした。
僕の母親は、この本に出てくる教育ママとは正反対で、完全に放任主義。ただ、僕が通っていたのは超進学校だったので、周りには勉強に必死な子も多く、「こういう経験をしてきたのかもしれないし、今まさにしているのかもしれないな」と、友人を見る目が少し変わりました。僕自身は勉強より剣道部で体を動かすほうが楽しく、そんな学生生活を送っていましたが、周りの優秀な子たちを見ては「どうやって育ったんだろう?」と考えるきっかけにもなりました。
実際に自分の周りを見ても、親の期待やプレッシャーのもとで勉強する子が必ずしも幸せとは限らず、自分でやる意味を見つけた子のほうが充実しているように感じたんです。「勉強って、やらされるものじゃないんだな」と実感し、自分でやりたいと思うことの大切さについても考えさせられました。
今は学生を指導する立場になり、「やる気を引き出すことが何より重要だ」とあらためて思います。当時は単純に面白い本として読んでいましたが、今振り返ると、自分の価値観を形作る一冊だったと思います。
『素直な戦士たち』
著者:城山三郎
出版・書影引用元:新潮社(新潮文庫刊)
『遥かなるケンブリッジ』
大学・大学院時代は結構本を読み漁りました。そんな中で最も人生に影響を受けた書籍の一つです。数学者である藤原正彦さんの本は、研究者としての姿勢や、留学に対する考え方に大きな影響を与えてくれました。この『遥かなるケンブリッジ』はイギリスのケンブリッジ大学に留学した際の体験に基づくエッセイですが、これに先行する作品として、アメリカ留学の経験を描いた『若き数学者のアメリカ』もあります。
『若き数学者のアメリカ』では、藤原さんがアメリカの学問の世界に飛び込み、奮闘する様子が生き生きと描かれています。一方、『遥かなるケンブリッジ』ではイギリスでの研究生活が綴られているのですが、2冊を通じて浮かび上がるアメリカとイギリスの学問の文化の違いがすごく鮮明で、特にイギリスのアカデミックな雰囲気に強く惹かれました。
僕自身、大学で研究を続けるうちに「留学してみたい」という思いが強くなっていました。そのときにこの本を読んで、「やっぱり海外で研究してみたい」と決断する大きなきっかけになりました。
何より、藤原先生の文章がとても面白くて、単なる体験記ではなく、冒険譚のようでとってもワクワクするんですよ。「留学ってこんなに面白いんだ!」と思わせてくれる。フランスに留学する前に何度も読みましたし、留学中も「ああ、こういうことか」と思いながら読み返しました。特に『遥かなるケンブリッジ』はヨーロッパの文化やアカデミアの雰囲気が詳しく描かれていて、フランスでの生活と重なる部分が多く、共感することがたくさんありました。
留学を通じて日本の研究環境とは異なる部分を知ることで、「自分もこういう世界で頑張ってみたい」と思えたし、自分の考え方の幅も広がったと感じています。けれどもしこの2冊と出会っていなかったら、僕は留学を決意していなかったかもしれません。それくらい大きな影響を受けた本です。
『遥かなるケンブリッジ』
著者:藤原正彦
翻訳:青木薫
出版・書影引用元:新潮社(新潮文庫刊)
『孤高の人』
これも大学時代に読みました。もともと冒険ものが好きだったこともあり、藤原正彦さんの本をきっかけに、藤原さんの父である新田次郎さんの作品にもハマりました。『孤高の人』は登山家・加藤文太郎の生涯を描いた小説ですが、加藤文太郎の生き方にとにかく衝撃を受けました。
加藤文太郎という人は、ほとんど単独行で厳しい山々に挑み続けた人です。登山といえば通常チームで行うものですが、彼は誰にも頼らず、自分の力だけで道を切り開いていった。その姿に強く惹かれました。
今から思えば研究者という道にも、これと通じるものを感じます。研究とは、誰も切り開いていない道を進む仕事です。特に自分の分野では、「誰もやっていないからこそ、自分がやるんだ」という感覚が常にあります。加藤文太郎が未踏のルートを単独で登っていったように、研究もまた、自分の意志で進む世界です。その精神が深く響きました。
ただ誤解のないように言っておくと、僕自身は取り立てて孤独が好きというわけではないです。むしろ人と話すのは好きですし、研究もチームでやるのが基本です。でも、「自分の決めた道を行く」という点ではすごく影響を受けたと思います。
研究も試行錯誤の連続であり、誰も正解を持っていない中で、自分で考えながら進めていくものです。そう考えると、『孤高の人』は単なる登山小説ではなく、人生の指針として読める本だと感じました。
『孤高の人』
著者:新田次郎
出版・書影引用元:新潮社(新潮文庫刊)
『唯脳論』
最後に、研究者として影響を受けた書籍として、養老孟司さんの『唯脳論』を挙げます。この本は、「心とは何か」「意識とは何か」といった根源的な問いに対し、脳の働きそのものが心の正体であるという視点を提示しています。最初に読んだのは大学時代だったと思いますが、正直、初めて読んだときは「すごい本だな」と思ったものの、すべてを理解できたわけではありませんでした。でも、何度か読み返すうちに、「ああ、こういうことだったのか」と腑に落ちることが増えていった本です。
特に印象に残っているのは、「心は脳が生み出す現象である」という考え方です。養老先生は、脳こそがすべての現象を作り出しているという立場で書かれており、それが当時の自分には衝撃的でした。
たとえば、「見えているものはすべて脳が作り出したもの」という話があります。私たちは普段、「目で見たものがそのまま現実」と思いがちですが、この本では「いや、それは違う。脳が処理したものを私たちは見ているんだ」と述べられています。その視点の転換は衝撃的でした。
自分の研究にも影響はすごく受けましたね。特に、「物事をどう認識するかは、脳の働き次第だ」という考え方は、今でもずっと頭の中にあります。科学は客観的であるとされますが、科学そのものが人間の定義した概念である以上、完全に客観的とは言えないのではないか。研究ということ自体、「結局は脳が生み出した世界を解析することなんじゃないか」と思うようになりました。実験においても「これは本当に客観的なデータなのか?」と考えるようになったし、こうした視点を持てるようになったのは、この本のおかげかもしれません。
『唯脳論』
著者:養老孟司
出版・書影引用元:筑摩書房(ちくま学芸文庫刊)
5冊に絞って振り返ると、今まで自分はそんなに情熱的なタイプではないと思っていたのに、影響を受けたのは結構、熱い本ばかりでしたね。挑戦、冒険、視点を変える──気づけばそんな本ばかりでした。自分の中に秘めている「熱さ」のようなものに気づく、よいきっかけになりました。
▼真下 知士先生にご登場いただいた過去記事はこちら
「Cas9がハサミなら、Cas3はシュレッダー」革新的なゲノム編集技術CRISPR/Cas3を開発した真下教授、その究極の夢とは | リケラボ
関連記事Recommend
-
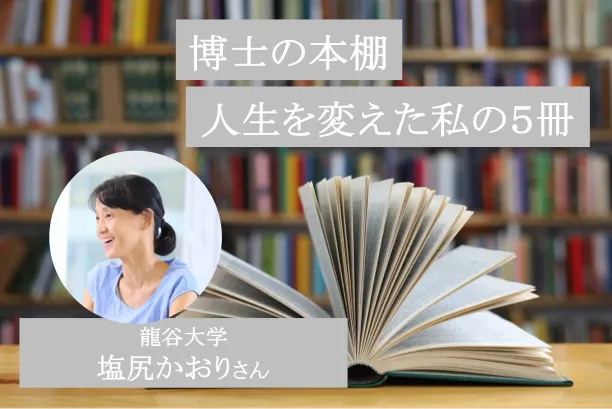
植物と虫の“匂い”を通じた会話を探究する生態学者、塩尻教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第12回)│龍谷大学 塩尻かおりさん
-
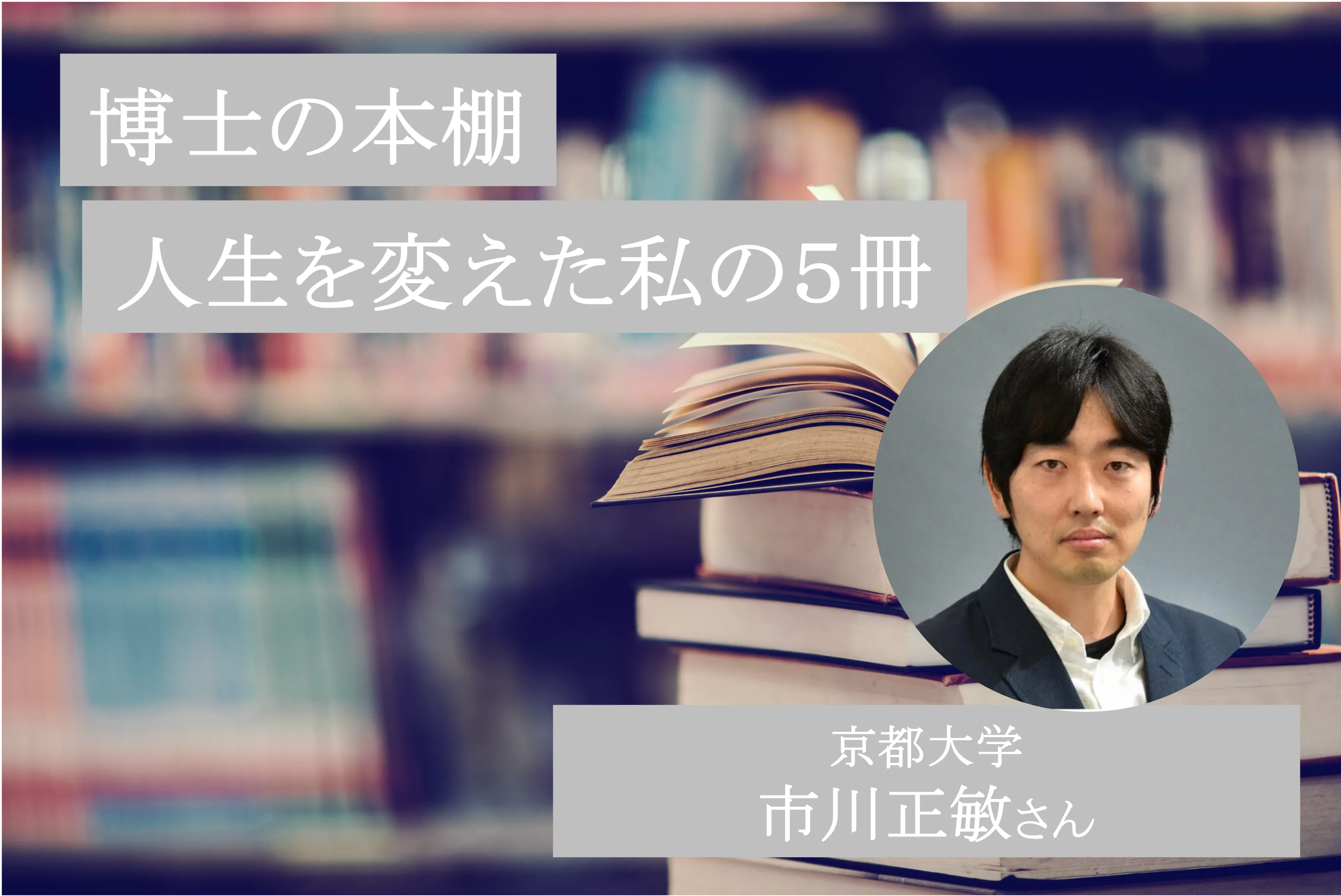
ソフトマター物理の観点から“生き物らしさ”を追求する市川正敏講師の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第10回)│京都大学 市川正敏さん
-
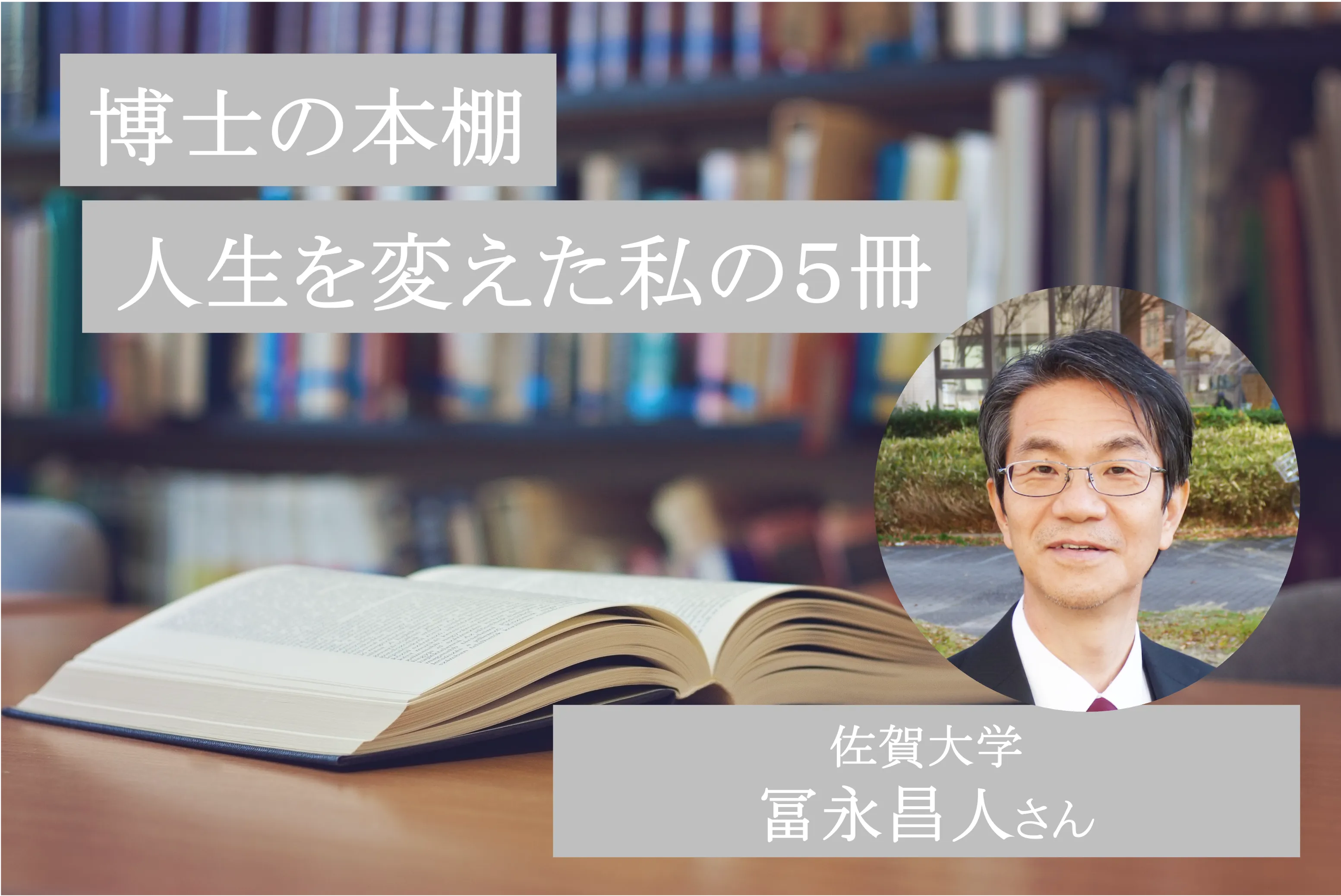
微生物が発電する「泥の電池」研究の第一人者、冨永教授に聞く「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第9回)│佐賀大学 冨永昌人さん
-
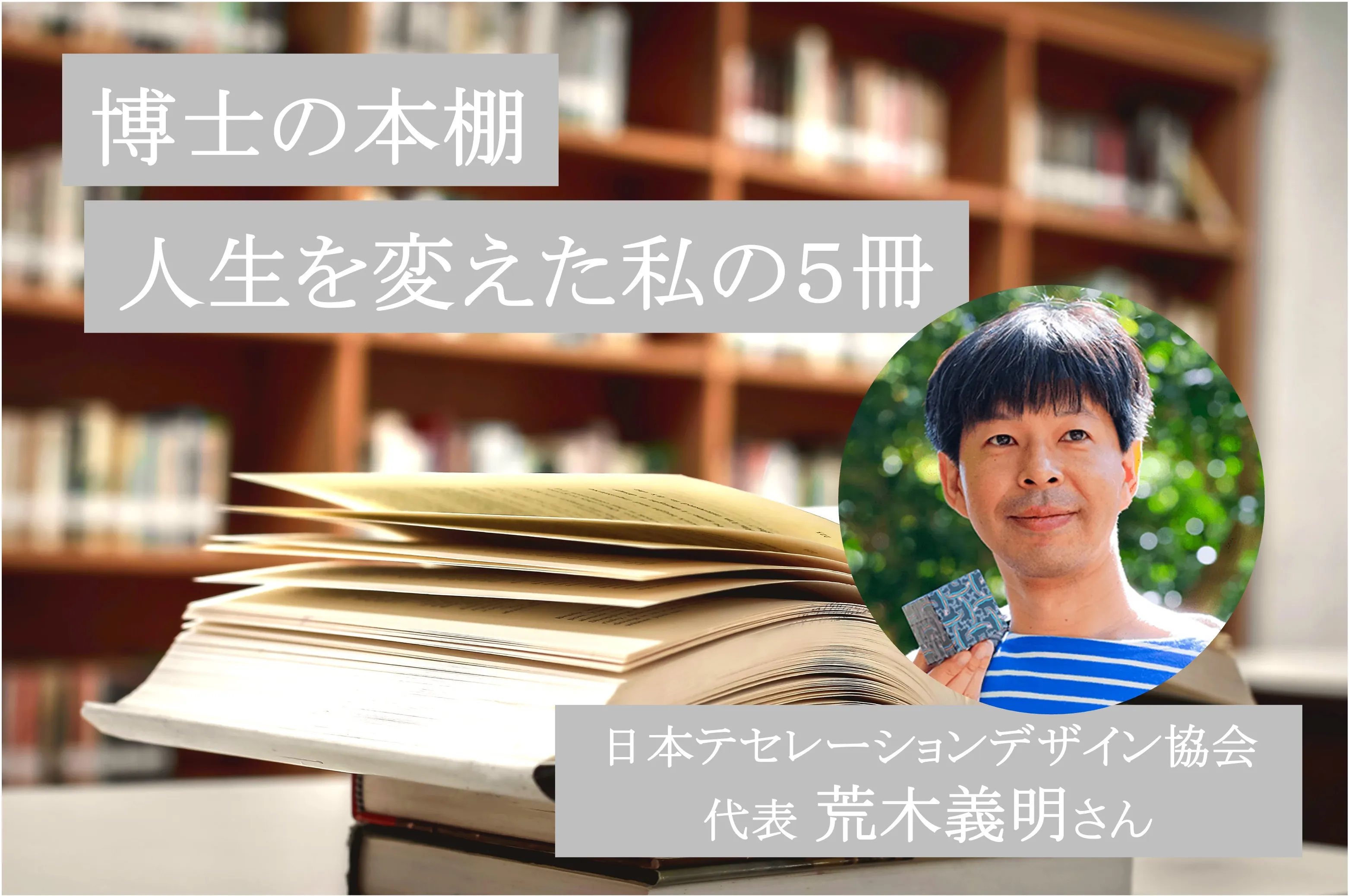
テセレーションデザインに見出す芸術性と法則。数学とアートを結びつける荒木義明先生の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第8回)│日本テセレーションデザイン協会代表 荒木義明
-
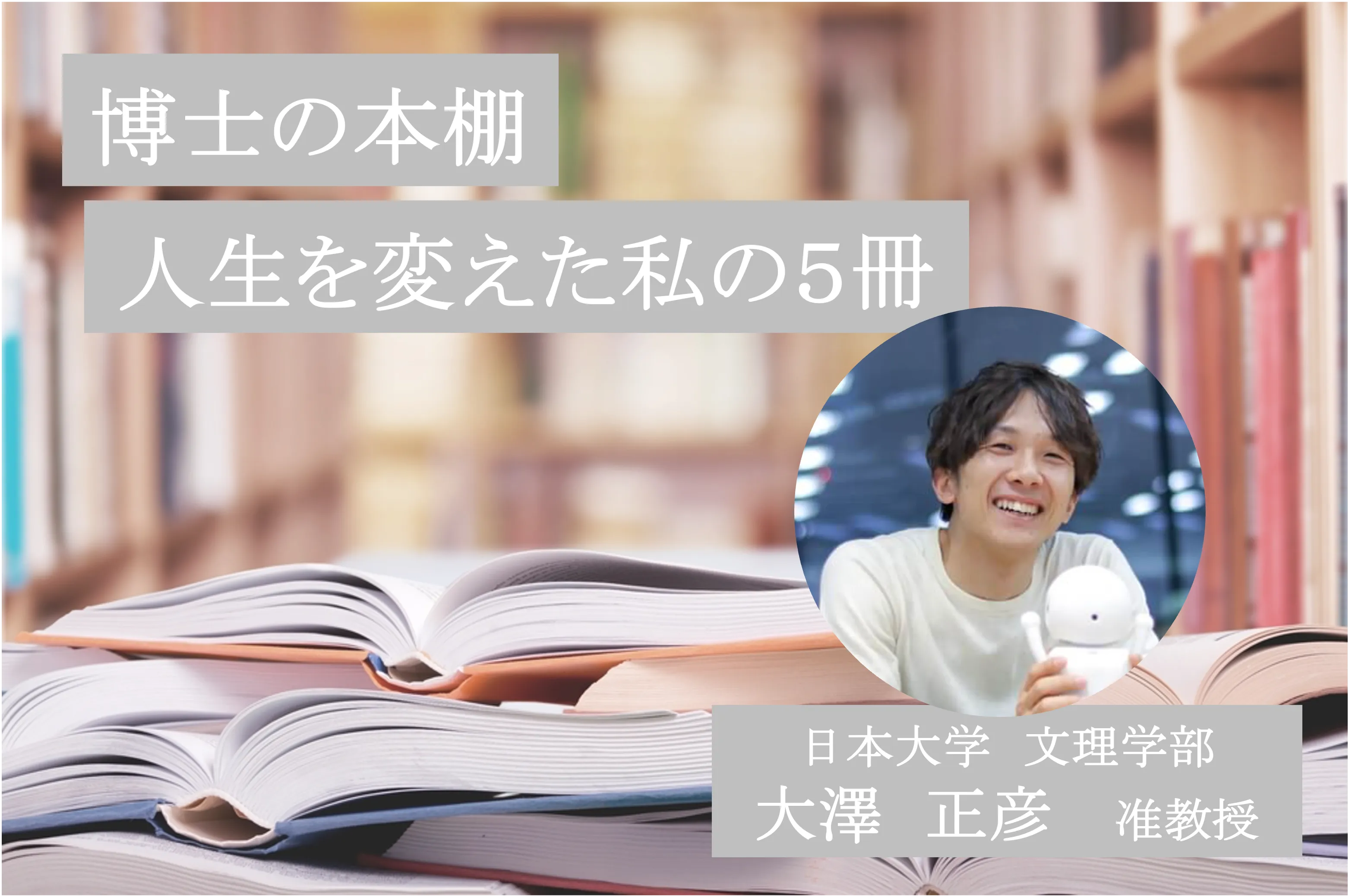
「ドラえもん®︎をつくりたい」人工知能開発の異端を育んだ個性のルーツとは?
博士の本棚(第7回)│日本大学 文理学部 大澤正彦准教授
-
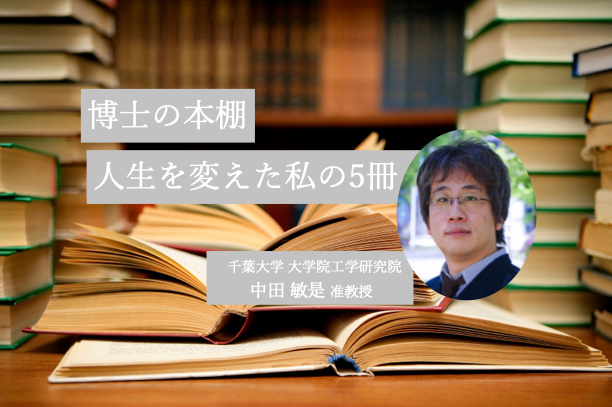
生物の飛行メカニズムを解明し、ドローンなどの機械工学へと応用する中田敏是准教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第6回)│千葉大学 大学院工学研究院 中田敏是さん
-
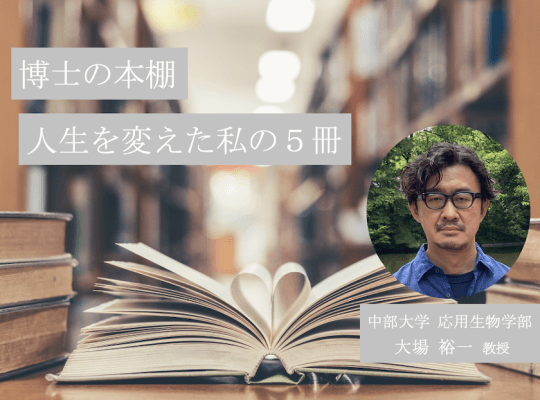
発光生物研究の第一人者、大場裕一教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第5回)│中部大学 応用生物学部 大場裕一さん
-
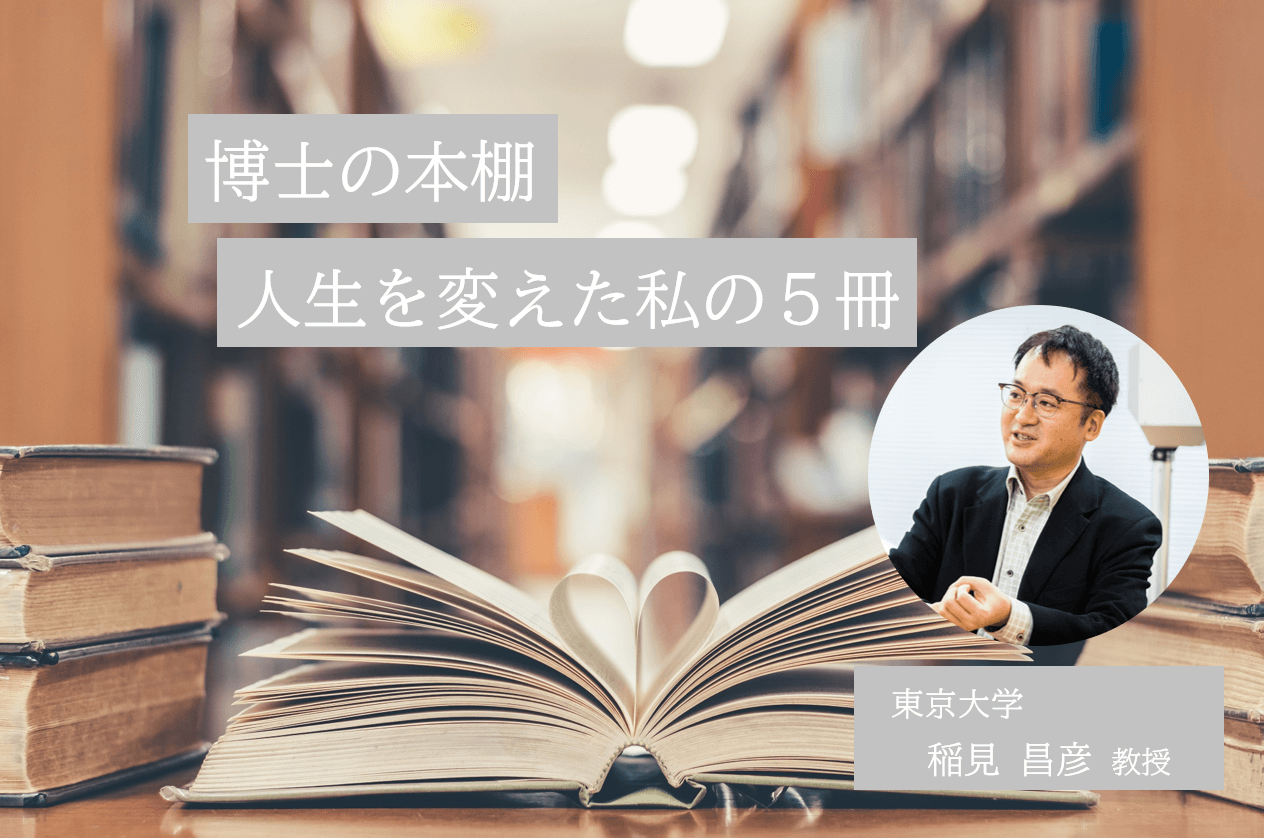
テクノロジーで人間の力を拡張する稲見先生の「私を形作った私の5冊」
博士の本棚(第4回)│東京大学 先端科学技術センター:稲見昌彦さん
-
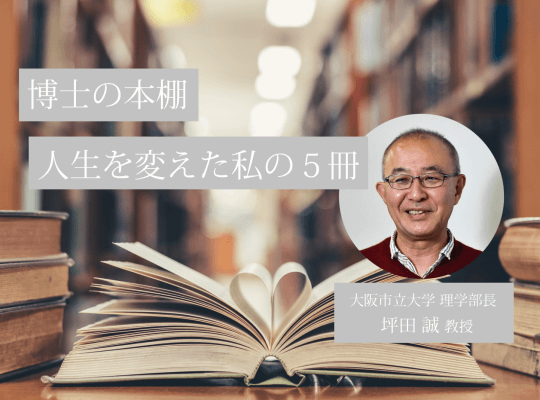
量子流体力学研究の第一人者、坪田誠教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第3回)│大阪市立大学 理学部長 坪田誠さん
-
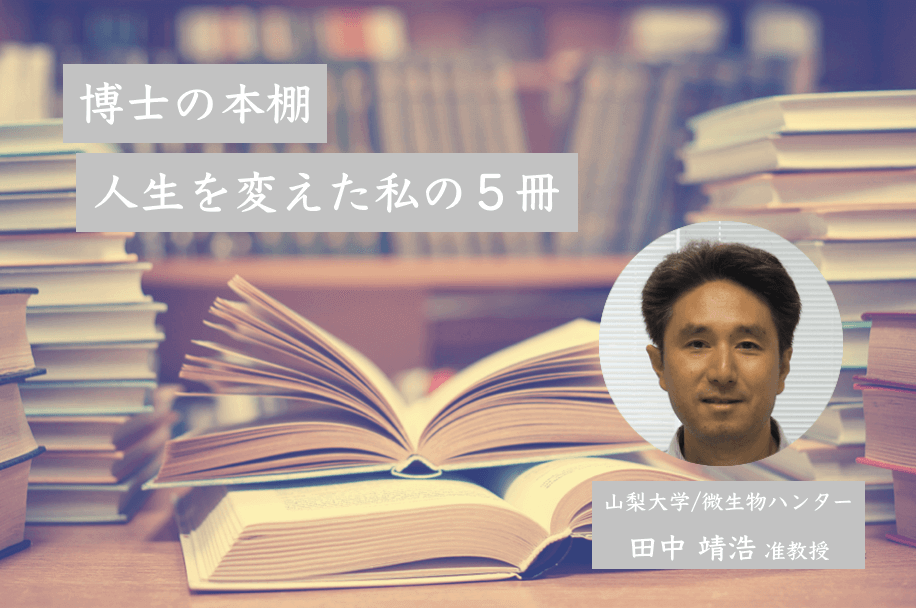
日本を代表する微生物ハンター・田中准教授の「人生を変えた私の5冊」
博士の本棚(第2回)│山梨大学生命環境学部 田中靖浩さん