リケラボは理系人材のための情報サイトです。
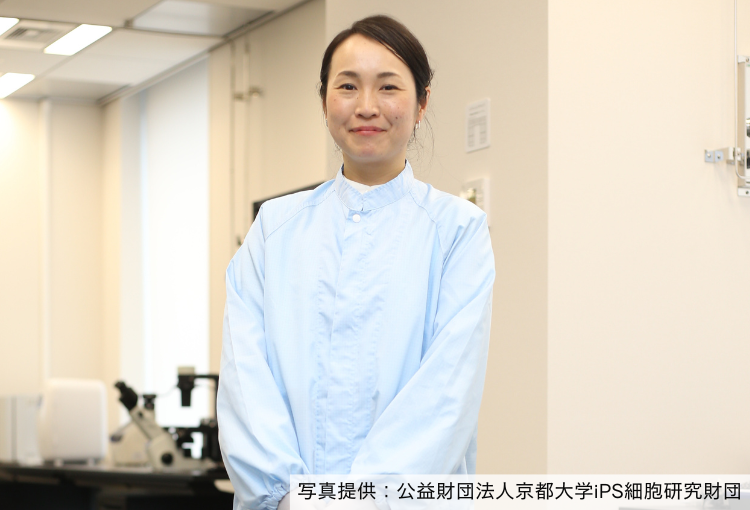
細胞培養の技術革新が切り拓く、iPS細胞の未来 ~チームと家庭とともに歩む、「面白そう」から始まった研究の道~
公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 研究開発センター ユニット長 北野優子
iPS細胞の社会実装を進める「my iPSプロジェクト」。このプロジェクトでは、個別化医療(自分自身の細胞からiPS細胞を作り出し、治療に活用すること)の実現に向け、iPS細胞の製造プロセスを自動化する挑戦が進められています。
公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団の研究開発センターでユニット長を務める北野優子さんは、iPS細胞技術の実用化を叶えるべく、細胞培養の技術革新に取り組みながら家庭と研究を両立する日々を送っています。高校時代に再生医療研究に興味を抱き、企業就職を経て、再び研究の世界へ。チームの力を大切にしながら、育児と研究を両立するしなやかな考え方に迫ります。
「憧れ」を原動力に発生生物学の道へ
──研究者になろうと思ったきっかけを教えてください。
海外の文化に興味があり、高校生の頃は、アナウンサーや英語を活かした国際的な仕事に憧れていました。ちょうどその頃、神戸に国立研究開発法人理化学研究所(以下、理研)の発生・再生科学総合研究センター(現:多細胞システム形成研究センター)が設立され、新聞で再生医療の特集を目にしました。「なんだかすごく面白そう!」とワクワクしたのが、理系に進んだきっかけです。数学は苦手だったんですけどね(笑)。
また、高校の近くに医科大学があり、医学系の研究に触れる機会も多かったことが影響しています。研究室見学などを通して、医療と研究のつながりに興味を持つようになりました。
──大学・大学院での研究内容を教えてください。
大阪市立大学(現:大阪公立大学)理学部生物学科に進学し、3年次に発生生物学の研究室を選びました。そこで、たまたま研究室のOBが理研で研究をしていたことが縁となり、大学に所属しながら理研で学ぶ機会を得ることができました。
さらに、研究を続けるために大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻に進学し、理研で線虫の細胞移動に関する研究を行いました。例えば、目や手足が適切な位置に形成されるためには、細胞がシグナルを受け取り、正しい方向へ移動する必要があります。そのメカニズムを解明することは、再生医療や組織工学にも応用できる可能性があり、とても魅力的なテーマでした。
──卒業後は再生医療研究の道に進んだのでしょうか?
いいえ、一度食品業界に就職しました。研究を続けるか迷った末、企業に入る道を選んだのです。学生生活で出会った優秀な研究者の方々も、任期制で雇用が不安定だったり、厳しい競争の中に身を置いていたりする姿を見て、研究の世界の厳しさを実感することがありました。また、当時はまだ転職が一般的ではない時代だったこともあったため「新卒で一般企業に就職する」という選択をしました。
入社した大手食品メーカーでは、商品開発を担当しました。研究とは異なる視点で「ものづくり」に関わる経験を積み、企業での開発プロセスを学ぶことができました。
──そこから研究の道に戻るきっかけは何だったのでしょうか?
グローバル企業での消費者向けの商品開発はやりがいがあり、貴重な経験でした。しかし、一方で研究への未練もありました。入社3年目の頃、研究職への転職を考え始めたんです。そこで、発生分野の応用技術を扱う研究室を探し、当時、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)に所属されていた渡辺亮先生の研究室にたどり着きました。
思い切って書類を送り、先生にお会いできることになったのですが、面談の結果、「今すぐではなく、もう少し経験を積んでから考えてみては?」とアドバイスをいただきました。次のキャリアについて、冷静に考えることを勧めてくださったのだと思います。
その後、会社には2年間在籍しましたが、「やはり研究を続けたい」という思いが強まり、再度渡辺先生に連絡しました。
── iPS財団への移行はどのような流れだったのでしょうか?
渡辺先生の研究室ではシングルセル解析などゲノム解析手法を用いて、細胞分化のメカニズムの解明や、iPS細胞の安全性評価など、安全で有効なiPS細胞の社会実装を見据えた研究を行っていました。研究室は実験系とデータ解析系のメンバーに分かれており、私は預かった検体を処理し、ライブラリ作成やデータ化を行う実験系を担当していました。
1年半〜2年ほど経った頃、CiRAにあった一部の部門が分離し、公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団(以下、iPS財団)として活動することになり、私はその流れでiPS財団に転籍し、研究開発センターに所属することになりました。
「自分の細胞からつくるiPS細胞」という未来に向けて
──ご担当されているmy iPSプロジェクトについての取り組みを教えてください。
iPS細胞は、皮膚などの体細胞に特定の遺伝子を導入することで、あらゆる生体組織に分化する能力を持つ人工多能性幹細胞です。iPS財団は、こうしたiPS細胞を再生医療分野へ実用化するため、産業界との橋渡し機能を担っています。
私が担当するmy iPSプロジェクトでは、患者さん自身の細胞からiPS細胞を作製し、個別化医療を実現するための技術開発を行っています。現在、iPS財団では免疫拒絶反応の起こりにくいiPS細胞をストック化し、汎用的に提供する仕組みを構築しています。しかし、この方法ではすべての患者さんに適合するわけではなく、一部の患者さんには免疫適合性の高いオーダーメイドのiPS細胞が必要になります。
ただし、現在のiPS細胞製造方法では、細胞の作製に時間とコストがかかるという課題があります。そこで私たちは、iPS細胞の製造プロセスを自動化し、より迅速かつ低コストで提供できる技術の開発に取り組んでいます。(詳しくは、iPS細胞の実用化に向けた挑戦 | リケラボ|ライフサイエンスのトピックス をご覧ください。)
──研究内容について教えてください。
最終的な目標は、iPS細胞の閉鎖型完全自動製造※を実現することです。しかし、そのためには単に機械を開発するだけでなく、多くの周辺技術の改良が不可欠です。例えば、細胞培養のプロセスを根本的に見直すことも重要な課題の一つです。
一般的に、iPS細胞は培養プレートに接着した状態で増殖します。そのため、細胞を継代培養(増殖した細胞を新しい容器に移して培養を継続すること)する際には、薬剤を使って接着を弱め、手作業で次のプレートへ細胞を移し替える必要があります。しかし、この手作業を機械に置き換えるには、高度な技術が求められます。
私たちは、iPS細胞を浮遊状態で培養できる技術の開発に取り組みました。もし細胞を浮遊状態で培養できれば、培養液の交換や継代培養を機械化することが可能になります。その結果、2021年には、iPS細胞の樹立から培養、さらには心筋細胞への分化までを、すべて浮遊状態で実施可能であることを実証しました。この技術により、iPS細胞の大量培養と自動化の可能性が大きく広がったと考えています。
※従来の細胞培養施設(開放型システム)では大型で高度なクリーンルームを設置し、作業環境全体の無菌化を確保する必要がある。一方、閉鎖型システムでは、小型の装置内で培養プロセス全体を外気から遮断する。そのため、無菌環境を保持しやすく、最終的にはクリーンルームの設置が不要となり、設備・製造コストの削減につながる。
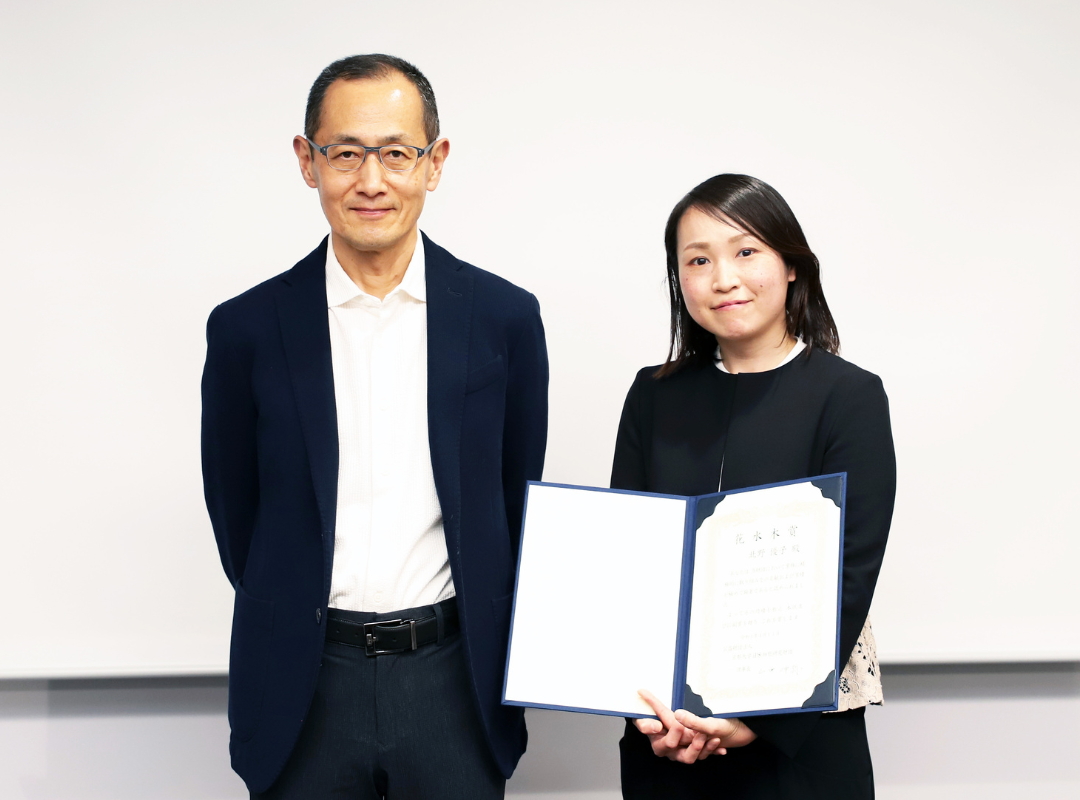
──自動化の課題やブレークスルーについて教えてください。
現在、最適な細胞培養条件を数値化する研究を進めています。実は、iPS細胞の培養は、熟練した技術者の「職人技」に依存してきました。細胞の状態を毎日観察しながら、培地交換や継代のタイミングを微調整する必要がありますが、こうした「感覚的な判断」を機械で再現することが最大の課題となっています。
私たちのアプローチは、細胞や培地の状態を数値化し、安定した培養に関与する要因を抽出することです。しかし、細胞の増殖や状態を左右するパラメータは非常に多く、それらを特定し、統計的に解析するには膨大な時間と作業が必要です。
まだ解決すべき課題は多いものの、細胞の状態をより正確に評価できるようになり、培養条件の最適化が少しずつ進んでいるという手応えを感じています。
家庭も職場も、助け合い、尊重しながら前に進む
──子育て中だとお伺いしていますが、どのような一日を過ごされていますか?
夫が単身赴任で現在北海道にいるため、小学校4年生と2年生の姉妹と3人で暮らしています。長女が3歳、次女が1歳の頃から夫の単身赴任が始まり、その頃にiPS財団への転籍も重なりました。仕事も生活も大きく変わり、慌ただしい日々が続いていたことを覚えています。
最近では、次女が小学校に入学したことで、登校の付き添いが不要になり、朝が少し楽になりました。9〜10時頃に出勤し、5〜6時頃に退勤。そこから買い出しなど生活の用事を済ませて、7時までには学童へ子どもたちを迎えに行きます。帰宅後は夕食をとり、宿題を見たり、習い事の練習をしたり。お風呂を済ませて、布団に入る頃にはとっくに10時を過ぎています。育児書には「8時に寝かせましょう」と書いてありますが、現実的にはなかなか難しいですよね(笑)。
──仕事と家庭の両立のコツはありますか?
忙しい時には、仕事も家庭も「どっちもできていない」と感じ、気持ちが追い詰められることがあります。そのため、私は家庭に関しては「完璧を求めない」と決めています。気になったところだけ、気づいたときに対応する、というイメージです。例えば、忙しい時には洗濯物を畳むことすらしません。子どもたちには「収穫」(=干してある洗濯物から必要なものを取る)や「宝探し」(=取り込んだ洗濯物の中から着るものを探す)をお願いすることもあります(笑)。ちょっとしたことも子どもたちと「楽しみながら」を意識するようにしています。
──職場のサポートはいかがですか?
iPS財団は、産休・育休の取得や時短勤務がしやすい環境です。制度が整っているだけでなく、現場の理解もあり、周囲の協力を得ながら仕事を続けられています。一方で、「子育て中だから理解してほしい」と一方的に求めるのは少し違うと感じています。同じ「子育て中」でも、それぞれの家庭環境やサポート体制などが異なるため、一括りにはできません。また、子育てに限らず、介護や病気で配慮が必要など、状況は人それぞれです。だからこそ、「子育て中だから特別扱いしてほしい」という考え方ではなく、誰もが尊重し合い、助け合える職場環境が理想だと思います。
今は、私自身がチームの中で迷惑をかけてしまうことのほうが多いと思いますが、少し下の世代のメンバーが私の姿を見て「ドタバタしながらも、どうにかやっていけるな」、「迷惑をかけることもあるけれど、お互い様だよね」と思えるような雰囲気が生まれるといいなと考えています。

人との出会いが、興味の先にある世界を広げる
──北野さんを動かすエネルギーについて教えてください。
最近、子どもたちが私の仕事を理解してくれるようになりました。iPS財団では、学会に子どもを帯同する際の費用の支援制度があるのですが、ある時、子どもが学会のプログラムを見てワクワクしていて驚きました(笑)。「夏休みの自由研究でiPS細胞のことをやる!」とも言ってくれたんです。そんな風に興味を持って応援してくれるのは本当に嬉しいですね。
また、子どもたちは私の仕事を誇りに思ってくれているのか、友達にも興味を持ってもらえるよう話しているようです。そうした期待を感じると、「もっと頑張ろう」というエネルギーが湧いてきます。私が取り組んでいるiPS細胞技術の研究が、実際の治療に応用される未来を見届けたいと思いますし、それが成功すれば、子どもたちにももっと誇れる仕事になるのではないかと感じています。
──これから研究の道を志す若者にメッセージをお願いします。
研究者は、「明確な研究テーマを持ち、それを極めていく人」だと思われがちですが、実は、私自身、特定の課題意識を強く持っていたわけではありません。研究を始めたのは、「最先端の研究とはどんなものなのか」、「すごい研究チームの一員になりたい」という純粋な憧れでした。また、今も「チームの皆と力を合わせ、患者さんの光になれるように貢献したい」という気持ちを原動力にしています。
大切なのは、好奇心や憧れを大切にしながら、まずは一歩を踏み出すことです。今はWEBやSNSで様々な情報が溢れています。「憧れの世界」を見ると「自分なんて…」と感じてしまうこともあると思いますが、結局のところ、経験してみないと分からないことだらけです。そして、その経験の中には、必ず「人」の存在があります。人との縁を大切にしながら、自分がワクワクする方向へ進んでほしいです。
北野優子(きたの・ゆうこ)
奈良県生まれ。大阪市立大学(現:大阪公立大学)理学部生物学科を卒業後、大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻修士課程を修了。大手食品メーカーにて食品開発に従事した後、研究の道に戻る。京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)・渡辺亮研究室にてシングルセル解析等を用いてiPS細胞技術の社会実装に取り組む。2020年、組織改編により京都大学iPS細胞研究財団へ転籍。現在は、同財団の研究開発センターに所属し、ユニット長としてiPS細胞製造プロセスの自動化に取り組む。2児の母として、家庭と研究の両立に挑戦中。
(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)
関連記事Recommend
-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?
-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?
-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)
-
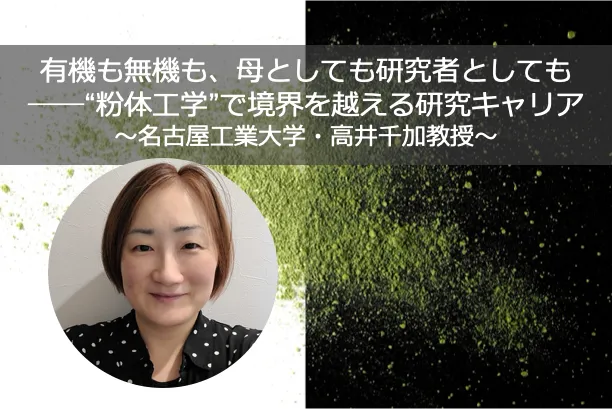
有機も無機も、母としても研究者としても──❝粉体工学❞で境界を越える名古屋工業大学・高井教授が実践するマイペースな研究キャリア
-

話題作『研究者、生活を語る』—担当編集者に聞く「『両立』の舞台裏」に込められた想い
-

研究者の育児と仕事について研究する中嶋先生に、ワークライフ・インテグレーションとは何か、聞きました。
~大阪商業大学 公共学部 中嶋貴子先生~
-

折り紙技術を駆使して宇宙から血管、さらに細胞にも活用。いつも自分で道を切り開いて歩み続ける研究者、繁富(栗林)准教授
-

女性研究職支援や助成金、女性向けの科学賞 まとめ
-

この植物の匂いって一体なに? 素朴な疑問から始めて、真相に迫っていく塩尻教授の研究スタイル
植物同士の驚きのコミュニケーション手法
-
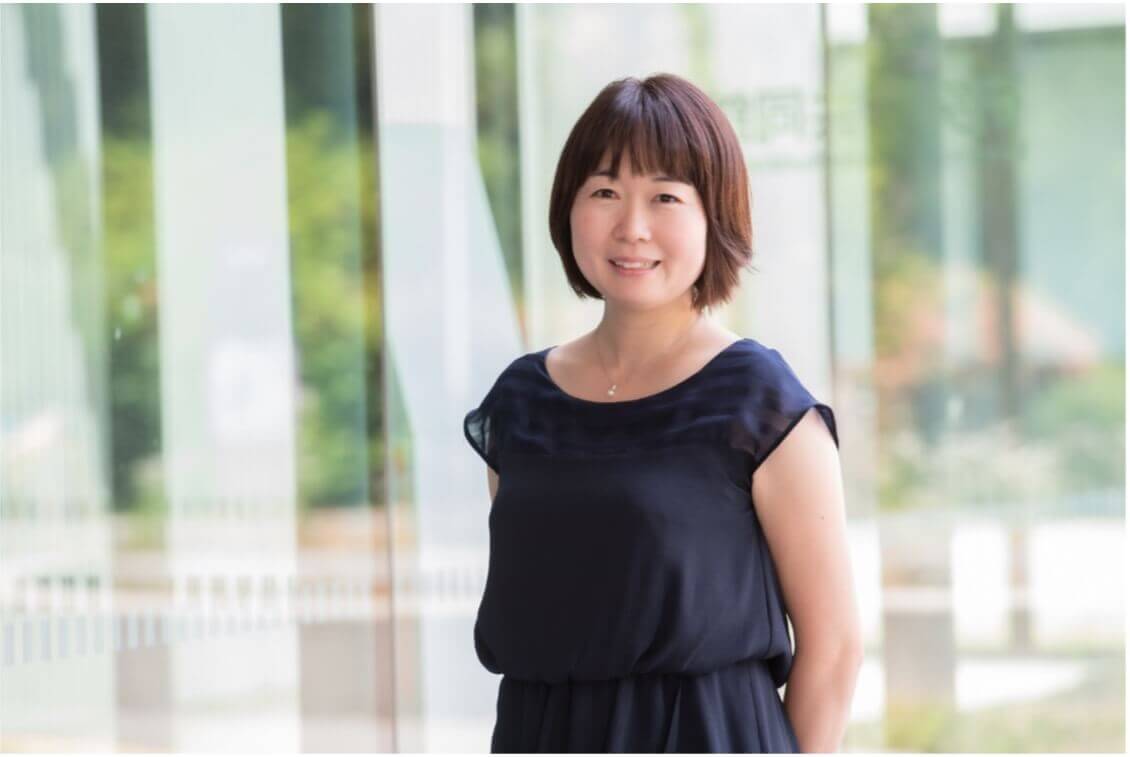
研究も人生も、自分らしくどこへ向かってもいい。世界初のナノ素材を開発し、単身で子育ても両立する鳴瀧教授の“サイエンス&ライフ”スタイル



